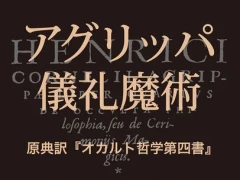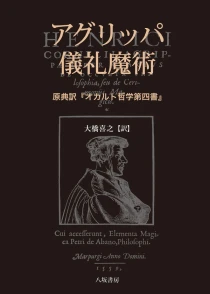連載
ルネサンス期の魔術教本に見る,自然科学の萌芽。「アグリッパ 儀礼魔術 」(ゲーマーのためのブックガイド:第37回)
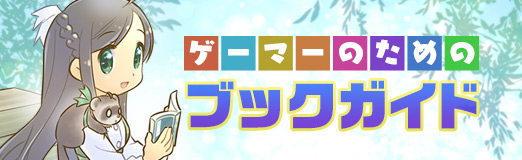 |
「ゲーマーのためのブックガイド」は,ゲーマーが興味を持ちそうな内容の本や,ゲームのモチーフとなっているものの理解につながるような書籍を,ジャンルを問わず幅広く紹介する隔週連載。気軽に本を手に取ってもらえるような紹介記事から,とことん深く濃厚に掘り下げるものまで,テーマや執筆担当者によって異なるさまざまなスタイルでお届けする予定だ。
魔術(もしくは魔法)といったら,あなたはどんなものを思い浮かべるだろう? 「ドカーンと一発,火の玉(ファイアーボール)」とか,エネルギー投射のようなものだとしたら(筆者が言うのもナンだが)ゲーム的な思考に毒されすぎである。「指輪物語」のガンダルフも,アーサー王伝説のマーリンも,そんな派手な術は習得していなかった。
この手の過激な攻撃魔法は1974年以降,RPGの元祖である「ダンジョンズ&ドラゴンズ」において発達し,広まった。火や悪辣な液体を吐いてくる竜がいるファンタジー世界である。人間側にも,それ相応の攻撃力が必要不可欠だったのだ。その衣鉢を継ぐ「ウィザードリィ」や「ウルティマ」,それから「ドラゴンクエスト」「ファイナルファンタジー」などコンピュータRPGにおいては,言うまでもない。
 |
映画「2001年宇宙の旅」の原作などで有名なSF作家のアーサー・C・クラークは,「充分に発展した科学は魔法と見分けがつかない」と喝破した。現代にはファイアーボールの代わりに拳銃,ライフル,ジャベリンにスティンガーなどなど,用途の異なるさまざまな火器がある。なかでも最大最悪なのが核兵器だろう。
歴史上の魔術師で,ファイアーボールを撃とうと思った人物を,筆者は寡聞にして知らない。せいぜいファウスト博士が,錬金術(≒化学)の実験を失敗して爆死した程度である。では彼らは魔術に何を求めたのか? 今回紹介する「アグリッパ 儀礼魔術」を紐解けば,その辺が少し見えてくる。
「アグリッパ 儀礼魔術 原典訳『オカルト哲学第四書』」
訳者:大橋喜之
版元:八坂書房
発行:2025年3月25日
定価:4500円(+税)
ISBN:9784896943764
購入ページ:
Honya Club.com
e-hon
Amazon.co.jp
※Amazonアソシエイト
八坂書房「アグリッパ 儀礼魔術 原典訳『オカルト哲学第四書』」紹介ページ
筆者がアグリッパの名前を明確に意識したのは,SFマガジン1979年10月臨時増刊号を手に取ったときだった。栗本 薫のグイン・サーガ外伝第1巻「七人の魔道師」が丸々掲載されていた号である。その七人のうちの一人が,こう描写されていた。
翌々年の文庫化では,加藤直之氏の手によるカラー口絵が添えられ,イグ=ソッグには夢に出そうなおどろおどろしい姿が与えられた。そして2000年10月に刊行されたグイン・サーガ本伝第75巻のタイトルは,そのものズバリな「大導師アグリッパ」であった。
栗本は,自作に歴史上の人物の名前や設定をよく援用した。このアグリッパという名前は,異端審問官による魔女狩りが横行し,マルティン・ルターによる宗教改革まっただなかの16世紀前半,ドイツで活躍した錬金術師・ヘンリクス・コルネリウス・アグリッパから拝借したものと思われる。
しかし錬金術師であれば,パラケルススことヴァン・ホーエンハイムのほうが有名ではないか? そのとおり,とくに「鋼の錬金術師」などのファンタジー作品に親しんだ読者なら,賢者の石や人造人間ホムンクルスの作成に関与したという伝説と共に,その名前を記憶しているに違いない。
実はアグリッパとパラケルススは,同じくトリテミウス修道院長という師に魔術を学んだ同門同志であった。そしてアグリッパは,「パラケルススがホムンクルスを作るのを見た」と語った人物でもある。こういう親和性のため,栗本は両者を融合して自作の登場人物としたのではないだろうか。
この本「アグリッパ 儀礼魔術」は,そんなアグリッパが記したとされる魔術書「オカルト哲学」三部作の続編にあたる「第四書」を翻訳したものである。前三部作がどちらかといえば理論的・概念的であったのに対し,第四書はとにかく実践に特化した副読本という位置づけで,大変意義深いものなのだが……いかんせんこの部分は40ページほどしかない。
本書のほぼ半分にあたる140ページは,第二次世界大戦前後のイタリアのオカルティスト,アルトゥート・レギーニによるアグリッパの伝記によって占められる。なので目次では第2部に当たるが,よほど魔術の腕に覚えがない限り,魔術書である第1部はすっとばし,彼の人と成りが分かる伝記の部分から先に読むことをオススメしたい。
さて,その伝記の部分だが,これは5章構成になっていて,第1章ではアグリッパにまつわる後世の伝説がまとめられている。これがまあ相当な盛りようで,アグリッパがいかにハッタリやホラ話が好きだったかがうかがえるものとなっている。
とはいえ,そうやってバシバシ周囲にモノを申さなければ,教会の闇に潰されてしまう時代だったのだ。ふとした誇張に尾ヒレがつき,話に花が咲き,やれ不死身だ,やれ今もどこかで生きていると言われるようになる。アグリッパは同時代の錬金術師・ファウスト博士を毛嫌いしていたというが,結局のところ同族嫌悪だったのではないだろうか。
第2章が伝記のメインとなる部分で,ここでアグリッパの不屈の生涯が40ページにわたって描かれる。彼は師トリテミウスの指導の元,後のライフワークとなる「オカルト哲学」三部作のうち第二部までを,23才で書き上げるのだった。
第3章は,当時の彼らが追究した魔術に関する概説だ。その概要を,誤解を恐れず筆者なりにまとめるなら,魔術とは「己の精神的習練や技術などによって,自身の魂をこの地上界から,天上世界(星界)を経由して神々の座である理想の世界に至らしめる」という道である。不思議な現象(いわゆる魔法)が生じる/生じさせるのは,その過程の副産物に近い。
続く第4章では,「オカルト哲学」三部作の成立と出版までの経緯が語られる。これらがきちんと出版されたのは1533年で,アグリッパが没する2年前であった。ただアグリッパの愛弟子であり,ともに黒死病や異端審問と戦ったヨーハン・ヴァイヤーは,師の目を盗み,それより前に勝手に「オカルト哲学」を写本していたという。
またこの章では,アグリッパの死から30年後に出版された本書の表題作「第四書」についても言及が行われている。もちろんアグリッパの作として出版された「第四書」だが,先のヴァイヤーは「師の作ではない!」と断言しており,「では,誰が書いたのか」は,今以て経緯不明の謎に包まれている。
ヴァイヤーは,自著である「魔神による幻惑について」の中で,「魔女とは医学上の問題であって治療できる可能性があり,自ら悪魔と契約した人々ではない」と,異端審問に真っ向から反対を表明している。
その思想は,もちろんアグリッパから受け継いだもので,かの心理学者ジークムント・フロイトも,自身の精神分析学の構築にあたり主要参考書とした「魔神による幻惑について」だが,残念ながら和訳本は出版されていない。
ただ69柱の魔神について解説した巻末付録「魔神の偽王国」だけは,のちにレジナルド・スコットの「魔女術の開示」に英訳のうえ再録されたことから,南條竹則氏による和訳が「悪魔聖誕 デビルマンの悪魔学」に「悪魔名鑑」として掲載されたことがある。「魔女術の開示」自体も訳本がないが,魔術研究&実践者の江口之隆氏のウェブサイト「西洋魔術博物館」に,一部だが和訳が掲載されているので,興味のある人はチェックしてみよう。
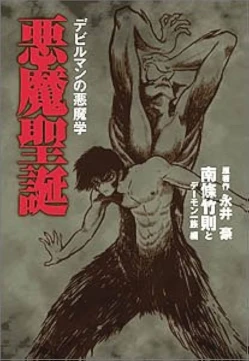 「デビルマンの悪魔学」(リンクはAmazonアソシエイト)。なお本書は後に「悪魔学入門 「デビルマン」を解剖する」と改題され再刊されたが,こちらは「悪魔名鑑」の部分が削られているので注意したい |
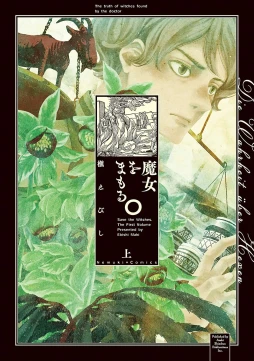 魔女狩りに対抗したヴァイヤーの奮闘を知りたい人にオススメなのが,槇えびし氏の漫画「魔女をまもる。」(リンクはAmazonアソシエイト)だ。全3巻+番外編の4冊で短くまとまっており,もちろんアグリッパも大活躍する |
話題が逸れた。アグリッパの伝記に話を戻すと,第5章は「オカルト哲学」三部作の内容の解説である。
この章を総括するなら,アグリッパは同書でまったく新しい概念を生み出したのではなく,新約旧約の聖書をベースにしながら,古今東西の魔術(つまりは当時の自然科学)関係の文献を整理し,編纂し,解説したのだ,ということになろうか。
三部作の第一部は,この地上世界(元素界)における自然魔術を扱い,これは後に我々の知る自然科学へと発展していく,その種にあたる。第二部は占星術で,これは後の天文学と数学に通ずる。第三部は,この本では「儀礼魔術」と翻訳されているものの解説で,儀式によって天使や精霊,魔神と交流し,そこから何らかの利益を得ようという魔術が記されている。
しかし若き日のアグリッパに,どうしてこれだけの知識をまとめることができたのだろう。実は師であるトリテミウスは,自身の務める修道院に,神秘学や魔術などに関する膨大な資料を集め,オカルト図書館を作っていた。アグリッパは,それを自由に読むことができたのである。
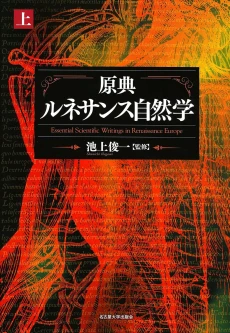 |
まず40ページある「第四書」の前半は,占星術的な精霊や邪霊の名前の「見出しかた」の術式やチャートである。だが「魔術の本質的な部分は書物には書けず口伝による」とアグリッパも書いてあるとおり,これを読んでも我々には霊たちの名前を導き出すことはできない。「ふーん」と参考にする程度である。
後半部分は実際の召喚/呪縛/祓魔といった儀式の解説で,こちらはなかなか興味深い。理解するには「オカルト哲学」第三部に記載の図などが必要になるが,これは本書の巻末にしっかり引用が用意されている。
さらには,これでは足りないと思ったのか,別の魔術師アバノのペトルス作の魔術書「ヘプタメロン」が,さらなる補足としてオマケで収録されている。オマケと言っても50ページ弱あるのだが,ここにはあらゆるシチュエーションに対応した天使の名が,表組されて掲載されている。名前を導き出せない我々へのヒントということなのだろう。
ルネサンス期のヨーロッパで,自然科学の祖となった魔術や錬金術を実践したアグリッパとその弟子ヴァイヤー。そして,同時代に生きたパラケルススやファウストらも含め,彼らに共通して言えるのは「医術の力で蔓延する黒死病(ペスト)の治療と撲滅に奮戦し,弁舌を振るって異端審問官と戦った」という事実である。稀代の哲人同士が交錯する,面白い時代だったのは間違いない。
本書はなかなか歯ごたえのある一冊だが,当時実際に魔術の教本として使用されていたことに想いを馳せるなら,読者の心の中に,確実に何か“気づき”めいたものを残してくれることだろう。
では,ケレパヤ! 皆々さまが息災であられますように。
■■健部伸明(翻訳家,ライター)■■
青森県出身の編集者,翻訳家,ライター,作家。日本アイスランド学会,弘前ペンクラブ,特定非営利活動法人harappa会員。弘前文学学校講師。著書に「メイルドメイデン」「氷の下の記憶」,編著に「幻想世界の住人たち」「幻獣大全」,監修に「ファンタジー&異世界用語事典」「ビジュアル図鑑 ドラゴン」「図解 西洋魔術大全」「幻想悪魔大図鑑」「異種最強王図鑑 天界頂上決戦編」など。ボードゲームの翻訳監修に「アンドールの伝説」「テラフォーミング・マーズ」「グルームヘイヴン」などがある。
八坂書房「アグリッパ 儀礼魔術 原典訳『オカルト哲学第四書』」紹介ページ
- 関連タイトル:
 Baldur's Gate 3
Baldur's Gate 3
- 関連タイトル:
 バルダーズ・ゲート3
バルダーズ・ゲート3
- 関連タイトル:
 Baldur's Gate 3
Baldur's Gate 3
- 関連タイトル:
 Baldur's Gate 3
Baldur's Gate 3
- この記事のURL:
キーワード
- PC
- RPG
- ドリコム
- ファンタジー
- プレイ人数:1人
- 連載
- PC:Baldur's Gate 3
- PS5:バルダーズ・ゲート3
- PS5
- Xbox Series X|S:Baldur's Gate 3
- Xbox Series X|S
- MAC:Baldur's Gate 3
- MAC
- ライター:健部伸明
- ゲーマーのためのブックガイド
(C)2023 Wizards of the Coast and Larian Studios. All rights reserved. Larian Studios is a registered trademark of the Larian Studios Games Ltd affiliates. Wizards of the Coast, Baldur's Gate, Dungeons & Dragons, D&D, and their respective logos are registered trademarks of Wizards of the Coast LLC