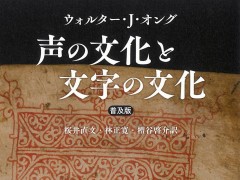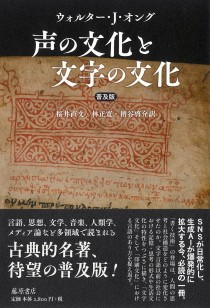連載
失われた“声の文化”に物語体験の限界を見る「声の文化と文字の文化」(ゲーマーのためのブックガイド:第50回)
 |
「ゲーマーのためのブックガイド」は,ゲーマーが興味を持ちそうな内容の本や,ゲームのモチーフとなっているものの理解につながるような書籍を,ジャンルを問わず幅広く紹介する隔週連載。気軽に本を手に取ってもらえるような紹介記事から,とことん深く濃厚に掘り下げるものまで,テーマや執筆担当者によって異なるさまざまなスタイルでお届けする予定だ。
この世界の文化には,「声」に由来するものと「文字」に由来するものがあるという。
どういう意味なのか一瞬考えこんでしまうが,こうして記事を書いているからには,筆者は後者の担い手ということになるのだろう。さらには今,この記事を読んでいるあなたも,きっと同じに違いない。ならば「声の文化」とはなんだろう。我々の知る「文字の文化」と,いったい何がどう違うのか?
これを解き明かしてくれるのが,今回紹介するウォルター・J・オングの著書「声の文化と文字の文化」である。原著は1982年と実に40年以上前の本だが,類例のない古典として読み継がれてきた名著である。斬新な内容のため翻訳には苦労したようで,日本語版が出たのは9年後の1991年。そのあたりの苦労話も知的好奇心を刺激するものがある。
そんな同書が2025年に,新版となって帰ってきた。この間のギャップを埋めるべく,訳者の一人である桜井直文氏が書き下ろした新たな解説「文字の文化以前以後」が巻末に追加されており,さらに参考文献リストには,それぞれの邦訳書も掲載されている。
「声の文化と文字の文化〈普及版〉」
著者:ウォルター・J・オング
訳者:桜井直文・林正寛・糟谷啓介
版元:藤原書店
発行:2025年5月30日
定価:2800円(税別)
ISBN:9784865784626
購入ページ:
Honya Club.com
e-hon
Amazon.co.jp
※Amazonアソシエイト
中学高校で6年も勉強するのに,多くの日本人は英語をしゃべることに抵抗感があるし,そもそもヒアリングが苦手だ。ところが「読むのなら少しはいける」という人は,そこそこいたりする。
なにせ日本人の識字率は99.9%以上で,世界一なのだ。7世紀には漢字を導入して「古事記」や「日本書紀」を書き,そこから9世紀になるまでにカタカナ/ひらかなを開発し,11世紀初頭には紫式部が世界最初の小説「源氏物語」を成立させ,江戸期には寺子屋で庶民までが読み書きソロバンを習った我々である。明らかに文字文化圏の民であるからして,声の文化圏はいわば異文化。苦手なのは仕方がないのかもしれない。
 |
そもそもこの地球上で確認できる最古の文字の痕跡は,紀元前3400年頃のメソポタミアである。シュメール人が帳簿の数字管理をするための数字記号を発展させた楔形文字で,基本的には日本語のカタカナ/ひらかなと同じ(子音と母音がセットの)音節文字だったようである。
その後いろんな地域でさまざまな文字が開発された。子音のみだった音素文字のフェニキア文字に,母音表記を加えたギリシア文字が元になり,現在のアルファベットとなった。日本でもローマ字として採用され,おかげでネットが発達した今も,気軽に海外とやりとりできている。
 |
この「イーリアス」をはじめとした古典では,神々がよく人間の運命に介入してくる。すなわち当時の人々は,神の声を聴いていたのだ。ところが時代が下るにつれ,神はいない,神は古代の英雄が神格化されたものだ,などという説が出てくる。この神の消失現象のことはジュリアン・ジェインズの「神々の沈黙」に詳しいが,本書ではその理由を,文字の普及によるものと説いている。
ここで「声の文化と文字の文化」の構成を見てみよう。
- 第一章:声としてのことば
- 第二章:近代における一次的な声の文化の発見
- 第三章:声の文化の心理的力学
- 第四章:書くことは意識の構造を変える
- 第五章:印刷、空間、閉じられたテクスト
- 第六章:声の文化に特有な記憶、話のすじ、登場人物の性格
- 第七章:いくつかの定理〔応用〕
第一章は序論で,二つの文化にはかなり圧倒的な違いがあり,文字文化に毒されている我々には,声のみの文化圏の人々の思考形態について想像すらできない,という事実がつきつけられる。
第二章および三章では,主題の一つである「声の文化とは何か?」が,丁寧に説明される。ここで「一次的な声の文化」とあるのは「二次的な声の文化」があるからだ。後者は,電子機器(録音機など)の発達によって声を(文字を介さず)直接的に記録/再生できるようになった現在であり,「一次的な声の文化」と共通の部分も多いが,文字文化の影響からは免れない。
第四章および五章は,逆に文字文化の特徴が論じられる。文字が読める特権階級のために手書きの写本が作られ,それが今度は庶民向けに木版や写植によって印刷された本となり,さらには電子化される。その段階ごとに,我々の文字文化は革新を迎える。大きいのは印刷による大衆化で,とくに西洋においては,これにより小説という物語形式が生まれた。
第六章では再び声の文化に戻り,とくに語られる物語についての特徴が深掘りされる。
第七章はいわば付録で,未来の研究者に向け,本書で充分に論じきれなかったさまざまな要素を提示し,ヒントとしている。
一読して驚かされたのは,やはり「声の文化」の特異性だ。とくに第六章に詳しいが,文字がないということは書物がないということなのだ。書物がない文化で物語を伝えてきたのは語り部や詩人といった専門職だが(ホメーロスもその一人),彼らも記録できないのだから記憶するしかない。この特殊な記憶術として生まれてきたのが,詩(韻文)という形式だったのだ。
詩には本来,(小説やエッセイなどの散文と違い)韻律や節回しなどのパターンがあった。日本の川柳や(短歌を含む)和歌に,音数,季語,枕詞といった決まりがあるように。日本最古の和歌は,スサノヲノミコトが詠んだとされる,
だが,冒頭の「八雲立つ」は,続く「出雲」に対する枕詞である。確かに出雲地方は年間の日照時間が少なく,雲に覆われがちな印象がある。同様に「飛ぶ鳥の」は「明日香」に,「神風の」は「伊勢」に,「ぬばたまの」は「夜」や「闇」に掛かる定型句である。
同様のパターンは「イーリアス」などギリシアのものにもある。「才知に長けた」はオデュッセウスに,「賢明なる」はネストールに,「レルネーの」はヒュドラーに,「ネメアの」はライオンに掛かる定型句だ。
北欧には,一つの単語を別の数語で置き換えるケニングという技法もある。例えば「海」と書かず「鯨の道」と置き換えるのである。
こういう単純な形容だけでなく,シーン描写にもパターンもある。ホメーロス作品の分析研究をしていたミルマン・パリーとその弟子アルバート・B・ロードが提唱した,口承定型句理論もしくは口誦定型句理論(oral-formulaic theory)がそれだ。
 |
例えば《浜辺に立つ英雄》という口承定型主題は,おおむね主人公/勇者が,(1)何らかの境界線(浜辺,橋,戸口など)に立ち,(2)部下など連れがおり,(3)それが旅の始まりもしくは終わりで,(4)そこに光や輝きがある……というパターンで,叙事詩や武勲詩などに頻出する。そして,これは勝利を示唆しているのである。
こういった各種の技法は,詩人や語り部が,いざ聴衆を前にして記憶を甦らせるために必要なテクニックであった。こうした詠ったり語ったりする場では,季節や時刻,天候,聴衆の状況などに合わせて,大筋は変えずとも,その時々に合わせて相応しい言葉を選んで紡ぎ直すのが普通だった。これは半ば機械的に無意識に行われるものなので,詩人や語り部は自身が創作した感覚を持つことなく,むしろ天啓や神の声によるものと思い込む。
そうして語られた言葉は聴衆を包みこみ,語り手も聴衆も,まるで自分が物語の主人公になったかのように,まさにそれが今起こったことのように追体験する。感覚の描写が五感を震わせる。
このように「内側から溢れ出てくるものを語る」という性質から,その内容は短めのエピソードになるしかなかった。長編詩であったとしても,それはエピソードを次から次へと続けていくという手法になり,そこに俯瞰的な視点による全体的なプロットの概念はなかったのだ。
この「全体を見渡したうえでのクライマックスとか起承転結といったドラマツルギー」が生まれるのは,台本として書かれたギリシア喜悲劇になってからである。とはいえ聴衆を相手に劇場で演じるものであるから,まだ声の文化(=聴覚に訴える)と文字の文化(=視覚に訴える)の中間でしかない。
やがて印刷技術によって同じ内容の本が大量生産されるようになると,著作権(Copyright)や作者といった概念が登場する。読書の主たる体験が,音読から黙読に移行し,やがて小説という形式が練られ,三人称視点の描写も発達し,作者は徐々に読者への語りかけをやめていく。
だがそれは,状況に合わせて再話することによる臨場感を失わせるものでもあった。生き生きとした描写が,通り一遍の――ときとして退屈な説明に堕してしまう可能性をも孕んでいたのだ。
これまで物書きとして暮らしてきた筆者としては,本書を通してそんな「文字の文化」の限界を思い知らされた次第である。よければこの書評を読んだ皆さんの感想も,聞かせてほしいものである。
 |
■■健部伸明(翻訳家,ライター)■■
青森県出身の編集者,翻訳家,ライター,作家。日本アイスランド学会,弘前ペンクラブ会員,特定非営利活動法人harappa理事。著書に「メイルドメイデン」「氷の下の記憶」,編著に「幻想世界の住人たち」「幻獣大全」,監修に「ファンタジー&異世界用語事典」「ビジュアル図鑑 ドラゴン」「図解 西洋魔術大全」「幻想悪魔第大図鑑」「異種最強王図鑑 天界頂上決戦編」など。ボードゲームの翻訳監修に「アンドールの伝説」「テラフォーミング・マーズ」「グルームヘイヴン」などがある。
- 関連タイトル:
 ブルーアーカイブ -Blue Archive-
ブルーアーカイブ -Blue Archive-
- 関連タイトル:
 ブルーアーカイブ -Blue Archive-
ブルーアーカイブ -Blue Archive-
- この記事のURL:
キーワード
- iPhone:ブルーアーカイブ -Blue Archive-
- iPhone
- RPG
- Yostar
- 無料
- Android:ブルーアーカイブ -Blue Archive-
- Android
- 連載
- ライター:健部伸明
- ゲーマーのためのブックガイド
(C)2020 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
(C)2020 Yostar, Inc. All Rights Reserved.