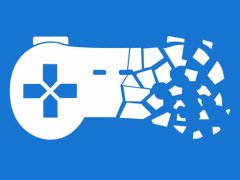業界動向
Access Accepted第831回:「Stop Killing Games」運動でゲーム産業はどう変わる?
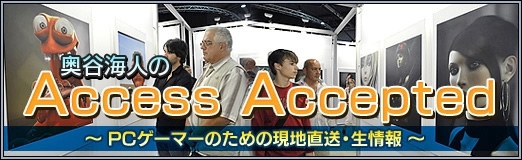 |
オンライン認証を必要とするようなゲームソフトのサービスが終了すると,プレイヤーは認証用のサーバーにアクセスできず,ゲームをプレイできなくなる。欧米では,「お金を出して買ったものは自分の自由にできて然るべき」という消費者意識が高く,こうしたサービス終了が,ゲーム業界やゲーマーコミュニティで大きな話題になっている。今回は,そんな状況で始まった「Stop Killing Games」という運動について紹介したい。
EUで始まった「Stop Killing Games」
「Stop Killing Games」(ゲームを殺すのをやめてください)という,刺激的な名前が付けられた運動をご存じだろうか? ことの発端は2023年12月に,Ubisoft Entertainmentが10年ほどのサービスを続けていたオープンワールド型レーシングゲーム「ザ クルー」のサポートの終了をアナウンスしたことだ。オンライン認証システムを必要とするゲームであったことからプレイそのものが不可能な状態となり,“過去の遺物”と化してしまう。そのことに疑問を持ったコンテンツクリエイターのロス・スコット(Ross Scott)氏がフランス政府に訴え出て,その後はオンラインでの抗議活動へと発展していった。
 |
当初は多くの賛同者を集められず,長らく50万弱の署名数に留まっていたが,6月24日になってスコット氏が「The end of Stop Killing Games」というタイトルのYouTube動画を公開する。詳しくは後述するが,これに多くのコンテンツクリエイターたちが反応を示し知名度が一気に上がって,この2週間ほどで大きな盛り上がりを見せた。日本時間の7月4日には,7月末日までの期限を残して,EUが審査を開始するのに必要な100万サインに達してしまったのだ。
そもそも,この「Stop Killing Games」とは何なのか? 公式サイトでは,以下のように説明されている。
「Stop Killing Gamesは,パブリッシャが顧客に販売したビデオゲームを破壊する行為の合法性に異議を唱えるために開始された消費者運動です。使用期限が明記されていないにもかかわらず,パブリッシャのサポートが終了するとすぐに完全にプレイできなくなるように設計された,事実上商品として販売されるビデオゲームが増えています。この慣行は計画的陳腐化の一形態であり,顧客に不利益をもたらすだけでなく,ゲームの保存を事実上不可能にしています。さらに,多くの国では,この慣行の合法性はほとんど検証されていません。」
欧米では,「一度購入したものは,完全に購入者に帰属する」という消費者権利(Consumer Rights)に対する意識が非常に高い。ゲーム市場においてもソフトを改造するMODや,生産中止されたハードウェアのゲームソフトをPCなどでプレイできるようにするエミュレータといったサブカルチャーを育んできた。デジタル化が進められてきた昨今のゲームエンターテインメントにおいては,「ザ クルー」のようにプレイヤー数が減少してビジネスとして成立できない状態になっていても,「権利を放棄してDRMを削除したり,プライベートサーバーで仲間たちとプレイできるよう対策をとってからサーバーダウンするべき」と感じる消費者が多いということだ。
 |
デジタル製品は,所有物ではなくライセンス販売
消費者の権利の範囲については,スコット氏も自身のビデオで明確にしていることだが,MMORPGのようなオンライン専用ゲームは,ライセンス契約を行うサービス形態であるとして,こうした訴えの中には含まれていない。MMORPGに何百時間のプレイタイムを費やしても,サブスクリプション型でサービスが進められるモバイルゲームで何十万円ものデジタルアイテムを課金しても,いつかはサービスが終了してしまうものなのだと,消費者はしっかりと理解したうえでプレイするという前提で成り立っている。
念を押しておくと,スコット氏は「ザ クルー」のサービス終了に合わせて「Stop Killing Games」を構想し始めたが,「ザ クルー」を名指ししてUbisoft Entertainmentを非難しているわけではない。ゲームパブリッシャの企業利益優先の考え方を,条例によって監督していくべきという主張をしているのみである。
しかし,Ubisoft Entertainmentは,本作のサービス終了にあわせて米国カリフォルニア州東部地区連邦地方裁判所などで,「DRMをアンロックするキーしかファイルにないのに,サービス終了のアナウンス直前まで,消費者を騙すかのようにゲームソフトを販売していた」と告訴されているような状況だ。DRM(Digital Rights Management)とは,デジタルコンテンツの不法コピーやチート行為を防ぐためのオンライン認証プログラムの総称である。
 |
これに対して,Ubisoft Entertainmentは訴訟の却下を求める申し立ての中で,ユーザーがゲームを購入した時点では「ゲームに対する無制限の所有権」は暗黙的に存在していなかったこと,そしてゲームの小売箱やデジタル版EULA(End‐User License Agreement / 使用許諾契約)に掲載された条件に従って,通知期間が経過したあとにサービスが停止されたことを強調している。
オンラインゲームプラットフォームの「Steam」を運営するValveも「デジタル製品は個人の所有物ではない」という立場を明確にするため,同サービスのEULAを2024年10月になって改訂し,ゲームを購入する際には「デジタル製品を購入すると,Steam上で製品のライセンスが付与されます」という新しい規約がショッピングカートに記載されるようになった。SteamはPCゲーマーにとってなくてはならないサービスであり,もし何かの理由である日突然,そのサービスがシャットダウンしてしまうことになると,もはや世界的な大事件になりそうだ。
それはともかく,Steamに関わらず反DRMを謳うGoG.com以外のほとんどのデジタルプラットフォームは,デジタル製品はライセンスを販売しているということを明確に表示するようになっている。
 |
ストリーマーたちの議論から再燃
「Stop Killing Games」が6月末から急激にスポットライトを浴びたのは,SNSでのストリーマーたちのディベートが大きな起因となったことは特筆しておくべきだろう。上記したスコット氏の映像「The end of Stop Killing Games」は,その序盤こそ思ったほど署名が集まっていないことを嘆いているものの,すぐにスコット氏が見つけた反論動画にアンサーするという,いわゆるリアクションビデオの1種に変わる。その反論動画は,自身がゲーム開発者としてゲーム業界の動向やゲームの論評,ゲーム開発の仕組みについてをPowerPointやMicrosoft Paintなどを使って評論するPirate Softwareことジェイソン・ソー・ホール(Jason “Thor” Hall)氏によって作成されたものだった。
その動画では,自身もプレイしている「World of Warcraft」を例にし,「すべてのゲームを永久的に個人でプレイ可能にするなんて不可能だし,結局は資金的に余裕のある大手パブリッシャが有利になるだけ」というような私見が述べられているが,上記したようにStop Killing GamesはMMORPGのようなオンラインゲームについては想定外であることなど,ホール氏のコメントには多くの誤解が含まれている。
そのことを,人気ストリーマーのpenguinz0(Cr1TiKaL氏)やAsmongold,Bellular Newsなどが取り上げてスコット氏の意見をサポートしたことで,「Stop Killing Games」が大きく注目されることになり,ほぼ不可能と思われた署名集めが実現しそうになっているわけだ。
 |
ホール氏は,今年初めに自身も所属するストリーマーだけが参加を許されているギルドメンバーによる「World of Warcraft」のライブ動画で,プレイヤーキャラクターがキルされると戻ってこられないハードコアモードをプレイ。その際に,マナが枯渇したことを理由に仲間を見捨てて逃亡してしまったという騒動を起こしてギルドから追放されるばかりか,視聴者からも嫌われてしまうという大炎上を起こして今も解消されていない。そうしたEU圏に住む“アンチ”たちが,「Stop Killing Games」の活動を知り,この1〜2週間のうちに署名に参加しているようだ。
これらの経緯もあって,欧米では大きな議論になっている「Stop Killing Games」だが,スコット氏はどのような条例が作り上げられるべきかという法的な内容までは言及していない。
一方で,2023年6月に2年ほどのサービスをもって終了した「Knockout City」は,2024年5月になってプライベートサーバーで仲間と楽しめるよう「Knockout City - Private Server Edition」がリリースされている。こういったゲームデベロッパ側の対応も増えているのは確かだ。つまり,「Stop Killing Games」の活動は,必要署名数を獲得したり,特設委員会が設置されて議論が行われたりするまでもなく,理解され始めているともいえる。
 |
特に大手パブリッシャの場合は,昨今のSNS事情から鑑みると,一度メーカーやブランドに傷が付いてしまうと,そこからゲーマーコミュニティの信頼を回復するまでに相当な時間と努力が必要になるのは明白だ。信頼を失わないために誰も読まないEULAを盾にするのではなく,開発時点でオフラインモードやプレイベートサーバーといったオプションを考慮し,最善を尽くしていくべきだろう。
日本からも「Stop Killing Games」に参加したいと考えるゲーマーは多いと思うが,署名はEU圏内からしか受け付けていない。しかし,この運動自体が日本のゲーマーにとっても有意義なものになっているのは間違いないはずだ。
著者紹介:奥谷海人
4Gamer海外特派員。サンフランシスコ在住のゲームジャーナリストで,本連載「奥谷海人のAccess Accepted」は,2004年の開始以来,4Gamerで最も長く続く連載記事。欧米ゲーム業界に知り合いも多く,またゲームイベントの取材などを通じて,欧米ゲーム業界の“今”をウォッチし続けている。
- この記事のURL: