インタビュー
[インタビュー]「The Outer Worlds 2」は,プレイヤーが自分の物語を紡いでいく仕組みを用意。キーパーソンが語った前作からの変化とは
本作は2019年に発売されたSFアクションRPG「The Outer Worlds」の続編だ。前作のテーマ性を受け継ぎながらも,舞台や主人公,そして物語が刷新されている。
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / [インタビュー]「The Outer Worlds 2」は,プレイヤーが自分の物語を紡いでいく仕組みを用意。キーパーソンが語った前作からの変化とは](/games/577/G057743/20250925063/TN/001.jpg) |
今回TGS 2025開催のタイミングで,来日したキーパーソンたちによるメディアブリーフィングと合同インタビューが実施された。4Gamerも参加してきたので,本稿ではその内容をお伝えしよう。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / [インタビュー]「The Outer Worlds 2」は,プレイヤーが自分の物語を紡いでいく仕組みを用意。キーパーソンが語った前作からの変化とは](/games/577/G057743/20250925063/TN/002.jpg) |
メディアブリーフィングに登壇したのは,Obsidian EntertainmentのVP of Development and Executive Producer(開発担当副社長およびエグゼクティブプロデューサー)を務めるJustin Britch氏だ。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / [インタビュー]「The Outer Worlds 2」は,プレイヤーが自分の物語を紡いでいく仕組みを用意。キーパーソンが語った前作からの変化とは](/games/577/G057743/20250925063/TN/003.jpg) |
本作の舞台は前作の「ハルシオン星系」から一転し,新たに「アルカディア星系」に変わった。ここは,恒星間航行技術「スキップドライブ」が生まれた場所であり,その副作用として宇宙に「時空の裂け目」(リフト)と呼ばれる現象が頻発している。
プレイヤーは,地球から派遣されたエージェントとして,アルカディアで任務にあたることになるのだ。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / [インタビュー]「The Outer Worlds 2」は,プレイヤーが自分の物語を紡いでいく仕組みを用意。キーパーソンが語った前作からの変化とは](/games/577/G057743/20250925063/TN/004.jpg) |
舞台の刷新に合わせて登場する勢力も一新された。独裁的で権威主義的な「護国帝政府」,狂信的な科学者集団「昇華律団」,そして前作で対立していた「アンティ・クレオ」と「スペーサーズ・チョイス」が合併して誕生した巨大企業「アンティーズ・チョイス」――アルカディア星系は,これらの組織の抗争によって引き裂かれており,プレイヤーはその渦中に巻き込まれていく。
ゲームプレイ面では,ObsidianらしいテーブルトークRPG風の要素が進化している。選択の積み重ねが仲間の運命や世界の行く末を左右するのはもちろん,キャラクタービルドの自由度もすこぶる高く,外交官から反逆者まで,プレイヤー次第でさまざまなロールプレイが可能だ。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / [インタビュー]「The Outer Worlds 2」は,プレイヤーが自分の物語を紡いでいく仕組みを用意。キーパーソンが語った前作からの変化とは](/games/577/G057743/20250925063/TN/005.jpg) |
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / [インタビュー]「The Outer Worlds 2」は,プレイヤーが自分の物語を紡いでいく仕組みを用意。キーパーソンが語った前作からの変化とは](/games/577/G057743/20250925063/TN/006.jpg) |
各地に現れた次元の裂け目とは,なぜか意思疎通が可能らしい。一体この裂け目は何なのか。そう筆者が質問すると「その謎や,根本原因を探っていくのが物語の核になる」とBritch氏は答えてくれた。
クセ強な3派閥の間でいかに“泳ぐ”かが面白い
作品の全体像が示されたあと,続いてゲームディレクターのBrandon Adler氏,デザインディレクター(アートではなくゲームデザインのほう)のMatt Singh氏への合同インタビューが行われた。こちらの内容をお届けして,本稿の締めくくりとしよう。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / [インタビュー]「The Outer Worlds 2」は,プレイヤーが自分の物語を紡いでいく仕組みを用意。キーパーソンが語った前作からの変化とは](/games/577/G057743/20250925063/TN/007.jpg) |
──βテストの反応はいかがでしたか。
Brandon Adler氏(以下,Brandon氏):
とても好意的でした。ただ,実際に触っていただいたのは作品のパーツをスライスしたような,ごく一部でしかなく,本番ではより広大で奥深い世界を体験していただけます。
Matt Singh氏(以下,Matt氏):
強調したいのは,プレイヤーの選択が早い段階から反映されることです。ガンプレイはもちろん,キャラクタービルドの自由度を通じて,遊びながら世界がどんどん広がっていくはずです。ワーッと開けていきますよ(笑)。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / [インタビュー]「The Outer Worlds 2」は,プレイヤーが自分の物語を紡いでいく仕組みを用意。キーパーソンが語った前作からの変化とは](/games/577/G057743/20250925063/TN/008.jpg) |
──前作の魅力を拡張した正統派の続編という印象ですが,大きな変化はどこにあるのでしょう。
Brandon氏:
まず前作でうまくいった点と,改善が必要だった点を整理しました。プレイヤーからは反応性や選択肢の幅をさらに望む声が多かったので,派閥やNPC,惑星を刷新し,物語の分岐も大きく広げています。
今回は選んだ派閥によって他派閥から締め出されることもあり得ます。1回のプレイでは見れなくなるものも出てきますが,その分新しい可能性が大きく開ける。そうしたダイナミックな変化を重視しました。
Matt氏:
仲間キャラも同じで,プレイヤーの方針に反対したり,場合によっては敵対関係にまで発展したりします。派閥やキャラクターの多様性が増し,風刺的な要素も含めて,より厚みのある世界が描かれています。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / [インタビュー]「The Outer Worlds 2」は,プレイヤーが自分の物語を紡いでいく仕組みを用意。キーパーソンが語った前作からの変化とは](/games/577/G057743/20250925063/TN/009.jpg) |
──ディープに楽しめそうですね。
Matt氏:
もちろんです。また舞台も主人公も違うので,「2」から入っても問題ありません。
──3つの派閥はいずれもクセが強く,簡単に肩入れできないのも面白いですね。
Brandon氏:
ユーモアは大事にしていますが,前作とまったく同じトーンではなく,3つの派閥を対比させる構造にしました。権威主義で全体主義的な「護国帝政府」,宗教的な科学者集団「昇華律団」,そしてクレオおばさんの「アンティーズ・チョイス」。それぞれ異なる価値観を持ち,プレイヤーは味方するのも敵対するのも,あるいは無視するのも自由です。
Matt氏:
私たちはプレイヤーが自分のストーリーを紡いでいく仕組みを用意しました。開発側がジャッジするのではなく,あくまで選択の自由を最大限に担保する。いわばゲームマスターとして舞台を整え,あとはプレイヤー自身に物語を作ってもらう形ですね。
──ゲームがプレイヤーの腕に合わせていろいろ調整してくれるという,フローシステムについて詳しく教えてください。
Brandon氏:
前作にも存在した仕組みですが,十分に生かしきれていませんでした。そこで「2」ではプレイヤーの行動をトラッキングし,プレイスタイルに応じた提案を行います。例えばリロードをよくするプレイヤーには,大容量マガジンを得られる代わり,リロード忘れでペナルティが発生する……といった具合です。メリットだけでなく,必ずデメリットも発生します。
Matt氏:
もともと“Flaw(欠点)”という意味合いで導入されたのですが,「2」ではネガティブな指摘ではなく,習慣をプレイスタイルとして強化する方向に改めました。自分の癖を個性として生かし,それをビルドに組み込める仕組みになっています。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / [インタビュー]「The Outer Worlds 2」は,プレイヤーが自分の物語を紡いでいく仕組みを用意。キーパーソンが語った前作からの変化とは](/games/577/G057743/20250925063/TN/010.jpg) |
──なるほど。何かもうひとネタ,少しブラックな笑いのある要素があれば教えてください。
Brandon氏:
(笑)。期待する答えかはわかりませんが,「ラジオ局」の要素も楽しいですよ。護国帝政府が流す堂々たるプロパガンダから,匿名の反体制派が海賊放送で発信する怪しげな番組まで,世界の裏側を知る手がかりになっています。プレイヤーがどの局を信じるか,どんな声に耳を傾けるかで,同じ状況でもまったく違った理解にたどり着くはずです。
また同じ「ガス漏れ」事件にプレイヤーがどう関わったか,ちゃんと解決したのか,利用して状況を悪化させたのかによって,その報じられかたも変わってきます。
──なるほど,「高度な情報戦」的なユーモアまで体験できるわけですね。最後に,日本のプレイヤーへメッセージをお願いします。
Brandon氏:
私は日本のRPGのファンでもありますし,日本の皆さんがRPGに求める要素,反応性や選択の積み重ねによる変化は,本作と非常に相性がいいと感じています。「The Outer Worlds 2」を通じて,日本と西洋のRPG文化をつなぐ橋渡しになればうれしいです。
Matt氏:
本作はまったく新しい舞台とキャラクターで,たくさんの選択肢を楽しめる作品です。PC,PS5,Xbox Series X|Sに加え,Game Passでも提供され,全編日本語に対応していますので,ぜひ気軽に遊んでみてください。
──ありがとうございました。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / [インタビュー]「The Outer Worlds 2」は,プレイヤーが自分の物語を紡いでいく仕組みを用意。キーパーソンが語った前作からの変化とは](/games/577/G057743/20250925063/TN/011.jpg) |
「The Outer Worlds 2」公式サイト
- 関連タイトル:
 The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2
- 関連タイトル:
 The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2
- 関連タイトル:
 The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2
- この記事のURL:


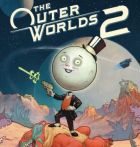





![[インタビュー]「The Outer Worlds 2」は,プレイヤーが自分の物語を紡いでいく仕組みを用意。キーパーソンが語った前作からの変化とは](/games/577/G057743/20250925063/TN/012.jpg)









