イベント
クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]
古代エジプトから始まり,古代ギリシア,古代ローマ,ルネサンス,バロック,ロココまでを取り上げた西洋服飾史は非常に盛りだくさんな内容だったため,各時代の主要なトピックを中心にレポートをお届けしよう。
なお,キャラクターデザインの一助となるクリエイター向けセッションではあるが,古代,中世を舞台にしたゲーム好きにも刺さる興味深い内容であったので,歴史ものが好きという人もぜひ目を通してほしい。
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/001.jpg) |
人間はなぜ衣服を着るのか?
社会的ディスプレイとしての機能
セッションの冒頭で朝日氏は,ファッションを俯瞰的に見るにあたり「人間はなぜ衣服を着るのか」という視点について述べる。
言葉そのままに捉えれば,身体を覆い保護する用途をイメージするところだが,これは「衣服はその時代ごとに何を表現し,どのような役割を担ったか」を問うものだ。この根源的な問いに対する答えとして,氏は「社会的ディスプレイ」としての機能を提示する。
西洋服飾史における衣服は,古代から18世紀フランス革命までは「権力の表示とその時代の究極の美を表現するもの」として捉えられていた。そのため,労働から解放された階級であることを示すように,あえて動きにくく,実用性を欠いた衣服を身にまとう傾向があった。
これが産業革命による布の大量生産,ミシンの発明による既製服が登場する19世紀以降になると,衣服の民主化が起きる。その結果,「ステータスシンボルとしてのブランド品,および自己欲求と個性の表現を周囲に示す」多様な機能を持つようになったという。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/002.jpg) |
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/003.jpg) |
また,服飾史を紐解いていくと,そこには時代や地域を超えて繰り返される,いくつかの普遍的なパターン(方程式)が存在すると氏は言及する。
1つ目は,「その時代の機能服やミリタリーウェアが,次の時代のフォーマルウェアになる(とくに男子服)」というものだ。身近なところでいえば,現代ではフォーマルウェアとして親しまれるスーツは,乗馬服が起源だと言われている。
20世紀ごろには,女子服が男子服のアイテムを積極的に取り入れる流れが生まれ,機能的な服が男子服のフォーマルウェアとなり,それが女子服に引用されるパターンが出来上がっていった。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/004.jpg) |
2つ目は,「インナーのアウター化」だ。この現象は西洋のみならず,世界中の服飾文化で観察される普遍的なパターンであり,日本でいうところの「小袖」も下着(インナー)からアウターへと転じたものの1つだそうだ。
Tシャツの変遷も同様で,第二次世界大戦までTシャツはアンダーウェアとしての位置づけだった。それが戦後,まずスポーツウェアや体操着として着用されるようになり,1950年代ごろにバンド名やメッセージをプリントしたものが登場すると,アウターとしての市民権を得た流れがある。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/005.jpg) |
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/006.jpg) |
ファッションの変遷をたどる
西洋服飾史(古代〜近世)
セッションの中盤からは,古代〜近世におけるファッションの変遷と時代ごとの特徴が解説された。ここからは,主要な内容をピックアップして紹介しよう。
●古代エジプト
この時代には,現代のアクセサリーのほぼすべてが出揃っていたと言われている。なかには文化として失われてしまったものもあり,ツタンカーメンの黄金のマスクにも見られる顎飾りがその代表例として挙げられる(耳にかけて顎に垂らす装飾品でつけひげ的なもの)。この時代で注目すべきは,カラシリスと呼ばれるドレスである。一見すると,現代的な縫製技術で作られたワンピースのように見えるが,実際は縫製に頼らず大きな布を身体に巻きつけ,留め具で形をとどめただけの衣服なのだという。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/007.jpg) |
●古代ギリシア
この時代に代表されるのは,ドーリア式キトンだ。カラシリスと同様に,大きな布を留め具と紐で固定して着用する構造が特徴である。このころは衣服によって身分が明確に示されておらず,ドーリア式キトンは男女共用の衣服として着用されていたそうだ。また,筋肉を模した青銅製の胴鎧や,金属片を貼り付けた布製の胴鎧,馬の毛で装飾されたコリント式兜など,機能性と装飾性を兼ね備えた装備も普及している。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/008.jpg) |
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/009.jpg) |
●古代ローマ
このころになると,衣服は一転して厳格な身分を表す装飾として位置づけられる。チュニック式のワンピースの上に布を巻きつけるトガは,その色,縁飾り,着方によって着用者の社会的地位を示していた。なかでも皇帝だけが着用を許されたトガ・ピクタは,ティロス貝から採取される希少な紫色で染められているのが特徴だ。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/010.jpg) |
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/011.jpg) |
●11〜12世紀
十字軍遠征による東西文化の交流が起こり,ヨーロッパでの服飾に対する意識が格段に向上。中近東から持ち帰られた美しいテキスタイルや高度な織物技術は,それまで比較的素朴だったヨーロッパの服飾文化に革命をもたらした。![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/012.jpg) |
●13〜15世紀
13世紀までのヨーロッパにおいては,長袖のワンピースに袖なしのワンピースを重ね着するスタイルが主流であり,男女の衣服はほぼ同一の構造だった。14世紀に入ると紋章入りのコタルディが一時的に流行(いわゆる家紋付きの服)。当時の主流であったチェインメイルは敵味方の識別が難しく,ビブスのように紋章入りのワンピースを上に着用したのがコタルディのはじまりとされている。
それが女性用のワンピースドレスに転用され,右見頃には嫁ぐ前の紋章を,左見頃には嫁ぎ先の紋章を配する独特のデザインも見られた。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/013.jpg) |
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/014.jpg) |
仕立ての技術が飛躍的な向上を遂げ,立体的な衣服が作られるようになり,衣服の男女差が明確になったのが14世紀中ごろ。このころには,13世紀まで主流だったチェインメイルに代わってプレート・アーマーが登場している。
鎧を身体にフィットさせるプレート・アーマーの製造技術は衣服の仕立てにも応用され,平面的な素材を立体的に構成する技術が確立されていった。
そして,その普及に伴い生まれたのが,プールポワンと呼ばれる綿を詰めたジャケットだ。もとは金属製のプレート・アーマーの下に着る機能服として生まれたが,やがて男性の正装として定着している。
当時の髪型も特徴的で,襟足を刈り上げたおかっぱのような髪型が多く見られる。これまた兜を被った際の痛みを軽減する狙いがあったそうで,この髪型は緩衝材のような役割を果たしていたらしい。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/015.jpg) |
男性の服装が機能的な服装へと移行する一方,女性の衣服はより装飾的な方向へと発展した。エナンやエスコフィオンと呼ばれるヘッドドレスがその1つで,既婚女性はこのヘッドドレスから出ている毛(眉や生え際)を剃るのが基本的なスタイルだったという。
●15〜16世紀
それまでの衣服が一体型の構造だったのに対し,ルネサンス期の衣服は複数のパーツを組み合わせて完成させるものへと変化した。身頃(胴の部分)と袖が別々に作られ,着装時に紐で結んで一つの衣服とする。左右の袖の色や素材を変えることも珍しくなく,アシンメトリーなデザインが意図的に採用されているのが特徴だ。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/016.jpg) |
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/017.jpg) |
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/018.jpg) |
●17世紀
ルイ14世の登場を機に,フランスがヨーロッパにおけるファッションの発信地となる。このルイ14世時代の前半に見られたのが,男性のスカートスタイル。西洋服飾史において,男性のフォーマルウェアがスカートだった唯一の時代だ。ラングラーヴと呼ばれるこのスカートは,キュロットスカートのような股付きのタイプもあれば,スコットランドのキルトの影響を受けた巻きスカートタイプもあったという。プールポワンは極端に短くなり,過度に長くなったシュミーズの袖,長髪のカツラ,ギャランと呼ばれるリボン飾りが,この時代の男性の正装として親しまれた。
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/019.jpg) |
この華美なスタイルは,ルイ14世時代の後半に実用的なジュストコールスタイルへと変化していく。膝丈のコート,ベスト,半ズボン,カツラという組み合わせは,その後の男子服の基本形となった。
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/020.jpg) |
●18世紀
ロココと呼ばれるこの時代,西洋服飾史における頂点を迎える。この時代を象徴するローブ・ア・ラ・フランセーズは,ファッション史のなかでも有名なドレスの1つとして数えられる。シュミーズの上にコルセットを着用し,理想的なウエストサイズである45cmになるよう身体を矯正する。パニエと呼ばれる腰枠でスカートを大きく広げ,独特のシルエットを作り出せば,おなじみのドレススタイルの出来上がりだ。
特徴として挙げられるのは,ピエース・デストマと呼ばれる胸の飾り布。この時代の女性たちが最も費用をかけたパーツであり,刺繍,宝石,レース,リボンで豪奢に仕立てられた。
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/021.jpg) |
![画像ギャラリー No.022のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/022.jpg) |
一方男性のファッションは,アビ・ア・ラ・フランセーズと呼ばれるコート,その下に着るベスト,クラバットと呼ばれるネクタイ,膝丈の半ズボンであるキュロットが基本的な構成要素だった。
興味深いことに,この時代は半ズボンがフォーマルウェアであり,長ズボンは船員や労働者が着用するカジュアルウェアという位置づけなのだとか。
中国趣味の美術様式シノワズリもこの時代を象徴する文化であり,弁髪からインスピレーションを得た髪型として,長い髪を後ろで束ねリボンで結ぶスタイルが流行している。
そして驚くべきは,1日の着替えの回数だ。上流階級の女性は日に4〜5回着替えるのだが,朝の部屋着から始まり,午前の訪問着,午後の散歩着,夜会用のドレスへと衣装を変える習慣があった。時間帯や赴く場所に合わせて衣装を変えるとは,まさに贅沢の極みだ。
マリー・アントワネットの時代になるとこの贅沢はさらに加速し,宮廷による浪費が民衆の怒りを呼び,フランス革命によって終焉を迎える。革命後のナポレオン時代には,それまでの華美な服飾文化は一転し,クラシックタイプかつ最小限の縫製で仕立てたシンプルなドレスが流行するようになる。
そうして200年を経て,今日のファッションの歴史へとつながっていく――。以上がセッションで語られた古代から近世における西洋服飾史だ。
![画像ギャラリー No.023のサムネイル画像 / クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/023.jpg) |
最後に朝日氏は,アニメ,マンガ作品で「あるべき場所に縫い目の線がない,前合わせが逆になっている,といった服飾の間違いを目にすることがある。時代に合った衣服の構造を理解すれば,描くべき線がおのずと分かるようになるはず」と,服飾史を学ぶ意義を示しセッションを締めくくった。
CEDEC 公式サイト
4GamerのCEDEC 2025記事一覧
- 関連タイトル:
 講演/シンポジウム
講演/シンポジウム - この記事のURL:


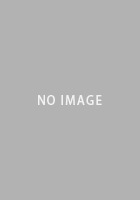








![クリエイターならば知っておきたい衣服が語る権力と美の物語。「西洋服飾史の流れ(古代〜近世)」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250723034/TN/024.jpg)








