イベント
パブリッシャは,インディーゲームのどこを見て契約を決めるのか。三社の見解が述べられた座談会をレポート[IDC2025]
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / パブリッシャは,インディーゲームのどこを見て契約を決めるのか。三社の見解が述べられた座談会をレポート[IDC2025]](/games/991/G999104/20251118029/TN/001.jpg) |
このセッションでは,PLAYISMの水谷俊次氏,room6の木村征史氏,講談社の片山祐貴氏が登壇し,三社のゲームパブリッシャが契約の際に見ているところを語った。本稿ではその内容をお伝えしよう。
セッションの冒頭では,チームの規模,年間のタイトル数に加えて,できることできないこと,といったそれぞれのパブリッシャの特色が紹介された。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / パブリッシャは,インディーゲームのどこを見て契約を決めるのか。三社の見解が述べられた座談会をレポート[IDC2025]](/games/991/G999104/20251118029/TN/002.jpg) |
まず,片山氏が講談社のできること(得意なこと)として挙げたのは,出版社というルーツを生かした編集業務だ。講談社ゲームラボに携わるスタッフは,漫画や小説の元編集者が多く,個人のクリエイターと伴走することを得意としている。こうしたサポートを個人のゲーム開発者にも届けたいという思いでパブリッシングを行っているという。
一方できないことは,「いろいろある」そうだが,自社でできないことも,知り合いのできる人と開発者をつなぐなどして,なるべく補えるような体制を整えていると片山氏は語った。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / パブリッシャは,インディーゲームのどこを見て契約を決めるのか。三社の見解が述べられた座談会をレポート[IDC2025]](/games/991/G999104/20251118029/TN/003.jpg) |
また,講談社はIPを生かしたゲーム展開も行っており,漫画の作者が興味を示した場合は実現することがあるそうだ。講談社からも「このIPを使えば,このゲームがもっと手を取ってもらえるかもしれない」と思った場合は,提案しており,「ザ・ファブル Manga Build Roguelike」は,まさに講談社の提案で実現したものだという。
漫画「ザ・ファブル」初のゲーム化作品「ザ・ファブル Manga Build Roguelike」本日発売。コマを配置して戦う「マンガ構築バトル」が登場

講談社ゲームラボは本日,新作ストラテジーゲーム「ザ・ファブル Manga Build Roguelike」を発売した。本作は,南 勝久氏の大ヒット漫画「ザ・ファブル」をベースにしたタイトルだ。漫画の登場人物を操作し,強敵が待ち受けるゴール地点を目指す“マンガ×デッキ構築型ローグライク”となる。
続いてroom6は,パブリッシャの一般的な業務(QA,翻訳,イベント出展,プロモーションなど)は一通り行えるとしつつ,特徴として日本国内で開発されたタイトル専門のパブリッシャであることを木村氏はアピールしていた。できないこととしては,大きくキャッシュを使うような業務で,高額な開発費の出資などは難しいとしつつ,月々で少額の支援などは検討するケースもあると述べた。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / パブリッシャは,インディーゲームのどこを見て契約を決めるのか。三社の見解が述べられた座談会をレポート[IDC2025]](/games/991/G999104/20251118029/TN/004.jpg) |
PLAYISMは,できること(得意なこと)として,翻訳業務を挙げた。もともとアクティブゲーミング・メディアがローカライズ業務を主としていた会社ということもあり,PLAYISMの中にも翻訳者がいるという。また,翻訳のボリュームが多い場合は,アクティブゲーミング・メディアの翻訳部署にヘルプを求めるということもできるそうだ。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / パブリッシャは,インディーゲームのどこを見て契約を決めるのか。三社の見解が述べられた座談会をレポート[IDC2025]](/games/991/G999104/20251118029/TN/005.jpg) |
そのほかにパブリッシャの違いとして話題に挙がっていた点としては,開発チームの有無だ。room6は自社で開発部門を持つが,PLAYISMと講談社は開発チームを持っていない。これに関して水谷氏は「リスクが怖いから」と語っていたが,他機種への移植業務などは行っているという。また,room6は講談社から発売されたタイトルの移植業務を手伝ったこともあると明かされていた。
タイトルの肝であるゲーム内容。見ているポイントは三者三様
今回のセッションは,主にパブリッシャが契約を決める際に参考にする「作品ピッチ資料」「Vertical Slice」「開発者自身」について,それぞれのパブリッシャが具体的にどこを見ているのかが語られた。
議題となった作品ピッチ資料は,ゲームの概要をとりまとめたものだ。タイトルやゲームコンセプトといったゲームに内容にまつわることを始め,予算や開発エンジン,ターゲットや販売予測などを記載する。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / パブリッシャは,インディーゲームのどこを見て契約を決めるのか。三社の見解が述べられた座談会をレポート[IDC2025]](/games/991/G999104/20251118029/TN/012.jpg) |
まず,ゲーム内容に関してroom6が見ていることは,ゲームジャンルだという。銃を撃ちあったり,剣で切り殺したりするような戦うゲームは販売しておらず,これまでも優しい雰囲気のゲームをリリースすることが多かったと木村氏は語る。
この理由としては,「僕自身があまり戦わないタイプだから」だそう。自社が展開するゲームブランド「ヨカゼ」の雰囲気と合わないということもあり,戦うゲームは敢えてリリースしていない。
room6といえばアドベンチャーゲームのイメージが強い読者も多いと思うが,ストーリーや世界設定については,かなり見ている部分だという。物語の結末もエンディングまで決まっている場合はなるべく教えてもらい,そこまでの過程がどう描かれる予定なのかもヒアリングし,契約の際の参考にするそうだ。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / パブリッシャは,インディーゲームのどこを見て契約を決めるのか。三社の見解が述べられた座談会をレポート[IDC2025]](/games/991/G999104/20251118029/TN/006.jpg) |
講談社が重視していることとして片山氏が挙げたのは,ゲームのコンセプトだ。社内では「型破りなゲーム/作者と伴走したい」というテーマがあり,その人ならではの独自性が光っているかどうかを大切にしているそうだ。
一方で,ジャンルやプレイ時間といった部分は気にしていないそうで,Steamの返金条件にもなる2時間未満の総プレイ時間でも,コンセプトが良ければいいという判断をしていると語った。
PLAYISMは,タイトルとゲーム内容が一致していることを,重視しているポイントとして挙げていた。いいゲームはタイトルが素晴らしいことが多く,ゲーム内容と一致している場合はうまくいくことが多いと水谷氏は語る。
さらに講談社と同じくコンセプトの独自性も大切にしているそうで,これは「似たゲームを売ることが難しいから」。例えば,開発者の理想を反映した「ファイナルファンタジー」のようなゲームを作ったとしても,そのゲームの良さをプレイヤーに分かってもらうまでのコストは非常に大きくなってしまう。独自性が輝くゲームであれば,そういった心配もない。
ジャンルに関しても,「Hollow Knight: Silksong」がリリースされ,成熟しているメトロイドヴァニアといったものよりも,「gogh: Focus with Your Avatar」のような時代に合った新しいものに心が動くという。もちろん,ジャンルだけで契約が決まるわけではないが,そうした部分も見ていると明かされていた。
Steamストアページは開く前に相談してもらえると嬉しい
ゲーム内容に続いて議題になったのは,開発に関する情報だ。
開発エンジンに関しては,UnityかUnreal Engineだとroom6でも手伝いができるため,ありがたいと木村氏は語る。講談社は特に開発エンジンについては絞っておらず,幅広く受け入れているそうだ。PLAYISMは,開発エンジンによって移植の際にかかる費用が変わるので,しっかり見ていると述べていた。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / パブリッシャは,インディーゲームのどこを見て契約を決めるのか。三社の見解が述べられた座談会をレポート[IDC2025]](/games/991/G999104/20251118029/TN/007.jpg) |
予算については,room6は基本的に出資しないスタンスだ。講談社は年間最大1000万円の予算を提供しているという。これは,2人で作ったときに暮らせる金額として出している。生活費を確保しつつ,アシスタント出したいなどの開発に必要な予算の要望があれば,追加で出資することもしている。PLAYISMは生活費程度なら支援したいとし,予算についてはそれぞれスタンスが異なるようだ。
開発スケジュールについては,一応聞くとしながらもあまり守られた試しがないと木村氏。水谷氏も開発者から言われたスケジュールに半年くらい足したくらいが目安だとみているという。片山氏も理想は1年から2年くらいでリリースできるといいと語るも,やはりインディーゲームの開発はおおむね延びるものであるとの見解をパブリッシャ側も持っているようだ。
ただ,リリース日というのは出資した資金が入ってくるタイミングであり,パブリッシャとしては重要な部分であると水谷氏は語り,精緻に作ったほうが望ましいとも語っていた。
ローカライズに関わる文字数に関して,講談社は10万字以内がありがたいとしつつ,ゲームに必要であればそれ以上を検討する場合もあるそうだ。一方room6は,特に文字数は制限がないという。さすがに1000万文字と言われれば考えるというが,基本的には気にしなくてもいいようだ。ちなみにこれまでにローカライズしたタイトルの中で最大の文字数は50万〜60万文字のものだそう。
続いて,販売についての情報についても触れられた。見解が共通して見られたのが,ウィッシュリストの登録数についてだ。ウィッシュリストの登録数については,3名とも特に気にしていないという。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / パブリッシャは,インディーゲームのどこを見て契約を決めるのか。三社の見解が述べられた座談会をレポート[IDC2025]](/games/991/G999104/20251118029/TN/008.jpg) |
Steamのストアページについては,講談社としてはむしろ企画の初期段階から関わらせてもらいたいそう。Steamのストアページは開いてないくらいで相談してもらえるほうが助かると,片山氏は語っていた。初出を重視しているのは,ほかの2名も同様で,木村氏も,どこにも出してない企画を持って来てくれると嬉しいと述べていた。
プロモーション期間に関しても,三社ともに発売日の半年前から3か月前くらいまでを目安に計画を立てていると語られていたので,早めに相談したほうがパブリッシャとしては助かるケースが多いようだ。
ピッチ資料の販売予測に関しては,三社ともに気にしてはいないという。販売予測やターゲット層などの見積もりは,そう簡単な話ではないので,ここを精緻に書くよりは,ゲーム紹介に時間をかけたほうがいいと水谷氏は語っていた。
ピッチ資料について一通り述べられた後は,Vertical Sliceについても触れられた。Vertical Sliceは,ゲームの美味しいところを切り出したデモ版のことで,完成版に近いものを短時間で遊べるものとしてパブリッシャに披露されることが多い。
これについては,PLAYISMは絶対にプレイして確認するというが,room6や講談社は企画書だけで契約するケースもあると語る。実際に講談社からリリースされた,「ダレカレ」は,企画書だけで契約に至ったタイトルなのだという。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / パブリッシャは,インディーゲームのどこを見て契約を決めるのか。三社の見解が述べられた座談会をレポート[IDC2025]](/games/991/G999104/20251118029/TN/009.jpg) |
契約は結婚に近い。人柄やSNSも気にする
セッションの最後は,開発者自身についてパブリッシャが見ているところが語られた。
まず講談社では,契約の際には必ず面談を行っており,顔を合わせてのコミュニケーションを重視しているそうだ。そして,最も重視しているのは,「その人が助けを必要としている人か」だと片山氏は言う。
パブリッシャは儲けの一部をもらってサポートをするので,その分の活躍ができないと意味がない。本当に他者を求めているかどうかを見ているという考えなのだそうだ。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / パブリッシャは,インディーゲームのどこを見て契約を決めるのか。三社の見解が述べられた座談会をレポート[IDC2025]](/games/991/G999104/20251118029/TN/010.jpg) |
room6は,基本的にゲームイベントに通ってゲームを見つけるというスタンスで,そこで開発者自身の雰囲気やふるまいを見ているという。また,SNSの発言も過去にさかのぼってチェックしていると語られた。SNSはゲームの内容以外にその人の性格を写す鏡で人柄を知る際の参考にしているようだ。
このように開発者の人柄について重視している理由として,木村氏は「契約は結婚やお見合いみたいなもので,その人と添い遂げられるかどうかという話だから」と語る。room6としても1作で終わる間柄ではなく,2作目3作目と仕事をしたいと思っているため,人柄はしっかりと見ているという。
PLAYISMもSNSはしっかり見ていると水谷氏は語る。やはりその人と組みたいと思えるかどうかは重要なポイントのようだ。一方で,過去の実績を重視するかという点については,3社ともに重視しないとの回答だった。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / パブリッシャは,インディーゲームのどこを見て契約を決めるのか。三社の見解が述べられた座談会をレポート[IDC2025]](/games/991/G999104/20251118029/TN/011.jpg) |
そのほかに見ているポイントとして,木村氏は「採択の判断材料にはしないが」と前置きしつつ,その人の現在のステータスも聞くようにしていると語る。未婚なのか結婚しているのか,学生なのか社会人なのかなどを聞くことで,接し方の参考にしているのだという。
また,片山氏は「この作品が,あなたの人生にとってどういう立ち位置なのか」ということは聞くようにしているという。1作目なのか,挑戦した作品なのかなど,開発者の目的を明確にし,タイトルの立ち位置をハッキリさせていると語られた。
それを聞き,水谷氏も「目指すゴールが共有できているか」ということは重要だと語る。そもそものゴールの認識や価値観がずれていると大事故につながることもあり,そこはしっかりと契約の際に共有する必要がある。
逆に言えば,「売ってくれる人を探している」というぼんやりとした探し方では,パブリッシャは見つからないのではないかと水谷氏は語っていた。
セッションの最後には質問コーナーも設けられた。そこで寄せられた2問への回答を記載して本稿の締めとしよう。
――別の業界からゲーム事業に参入しているというニュースを最近よく聞きますが,これについてどう思われていますか。
木村氏:
インディーゲームは盛り上がっているように見えますが,世間一般ではまだまだ認知度が低いです。市場規模も大きくないので,盛り上げてもらうこと自体はプラスであると考えています。ただ,儲からないなと思ってすぐに撤退することはやめてほしいなと思っています。
片山氏:
我々はまさに別の業界から参入した側なんですが,それを抜きにしても,異業種からの参入はいいことだと思います。出版社や映画会社などそれぞれの業界の強みを生かせますし,市場のパイを増やす役割も担ってくれると思っています。
水谷氏:
誤解を生む言い方かもしれませんが,私はいい意味で何とも思っていないんです。インディーゲームって何回かこういうブームがあるたびに,いろいろな会社が参入してきて,しばらくするといなくなるということを経験しているので……(笑)。
それによって自社のゲームがめちゃくちゃ売れるようになったり,売れなくなったりすることもあまりないので,気にせずに自分のやりたいことをデベロッパさんとやろうと思っています。
――契約する際にチームの規模を気にすることはありますか。
水谷氏:
開発チームが増えると予算が倍増するので,1人のほうがいいなと思うことは正直あります。30人,40人規模のチームだと,僕らもそのタイトル1本に集中しなければならないので,現実的に難しいんです。なので,10名以上のチームは基本的にお断りすることが多いです。
木村氏:
人数は気にしたことはないんですが,多いと維持が難しいと思うんです。リーダーがいて,その作家に求心力があって,ほかのスタッフが心酔しているとかであればいいんですが,人数が多いと仲違いすることもありますし。なので,多くて3〜4名くらいが理想と思っています。
片山氏:
講談社の場合は,個人を支援する「ゲームクリエイターズラボ」と,法人と一緒にものづくりをする「ゲームクロスラボ」で分けています。あと,木村さんもおっしゃってましたが,チームの全員が同じ方を向くというには,誰がその作品の責任者なのか明確にするというのは,重要なことだと思います。
- 関連タイトル:
 講演/シンポジウム
講演/シンポジウム - この記事のURL:


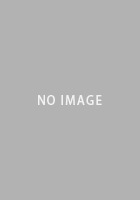








![パブリッシャは,インディーゲームのどこを見て契約を決めるのか。三社の見解が述べられた座談会をレポート[IDC2025]](/games/991/G999104/20251118029/TN/013.jpg)









