連載
Access Accepted第843回:盛り上がるローカルヒーローのアクションアドベンチャー
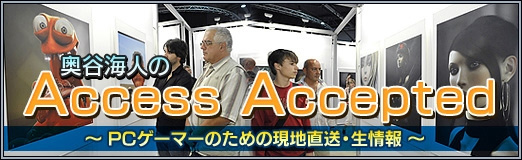 |
ここ最近のアクションアドベンチャーを見渡すと「キングダムカム・デリバランス II」や「Ghost of Yōtei」のように,地元の歴史や文化を真正面から扱った作品が目立つ。源流を「アサシンクリード」シリーズに求めるのは容易だが,今はその文脈がさらに細分化し,地域ごとの知られざる歴史に光を当てるローカルデベロッパが存在感を強めている。今回はそんな“地元発ヒーローもの”の新作を紹介したい。
世界各地の歴史や人物を描くアクションADVが増えてきた
20世紀,ゲーム産業は日米欧の大手が中心だった。しかしオンライン配信の普及と開発環境の低価格化によって,ゲーム制作は“どこの国でも可能なエンターテイメント”へと変質した。最近では各地の開発者や,大手から地元へ戻って再出発する人材が存在感を増し,規模の大小を問わず「自分の土地の物語を,自分の手で作る」動きが顕著になっている。
技術面でも,パフォーマンスキャプチャやフォトグラメトリー,レイトレーシングなど,かつて一部の大手しか扱えなかった手法が一般化し,SNSによるプレイテストや情報発信も相まって,開発現場の“民主化”は想像以上の速度で進んでいる。
翻ってゲームのテーマについて考察してみると,チェコのWarhorse Studiosが手掛けた,中世ボヘミアの歴史をバックグラウンドにする「キングダムカム・デリバランス II」,江戸初期の北海道や鎌倉時代や対馬にスポットをあてた,Sucker Punch Productionsの「Ghost of Tsushima」や「Ghost of Yōtei」などの人気が高い。さらには有名な伝承ながらも欧米では余り認知されていなかった西遊記をダークに描いた「悟空: 黒神話」などが,アクションアドベンチャーをけん引している。
 |
その源流は,2007年に始まった「アサシンクリード」シリーズにあると思うが,ファンタジーに歴史を絡ませることで,ある種の真実性(オーセンティシティ)がストーリーの背景にどっしりと鎮座するわけだ。
今年は初めて実在人物を主人公に日本の中世を舞台にした「アサシンクリード シャドウズ」が発売されたものの,評価が分かれる残念な結果となり,Ubisoft Entertainmentも大きな変革期を迎えることになった。
アサシンクリードシリーズは,これまでカリブ海の海賊や北欧のバイキング,古代エジプトや近代フランスなど,興味深い史実が描かれてきたが,サムライやニンジャが登場する中世日本は,「アサシンクリード」のファンコミュニティにとっても最も切望されるテーマの1つだったとされる。
また,新興国のゲーム開発者たちが,どれだけ「自分の国の歴史がテーマになればうれしいのに!」とか,「自分の国にも面白い歴史やゲームとして残すべき題材がある!」と思っていることは想像に難くない。「キングダムカム・デリバランス」のような成功例を追って,彼ら自身も自分の国にスポットライトをあてたゲームを作ってみようと考えて不思議ではないだろう。今回は,そんなローカルデベロッパによる,次期公開予定の新作を3つ紹介してみたい。
 |
オスマントルコ建国者の父“エルトゥールル”
「Ertugrul of Ulukayin」
トルコのTekden Studioから6月にアーリーアクセス版がリリースされ,現在も定期的なアップデートが進められている「Ertugrul of Ulukayin」は,オスマン帝国の建国者であるオスマン一世の父として13世紀を生きたエルトゥールル・ガジ(Ertugrul Ghazi)とその仲間達が描かれるゲームだ。
アフラト山麓の美しい草原を腐敗させようとする秘密結社と,その背後に潜むモンゴル勢力や伝承上の神獣たちと戦いながら,世界の鍵を巡る陰謀を解き明かしていくことになるという。
本作には,剣技をこなすオーソドックスな戦士のエルトゥールルのほかにも,片手で斧を振り回すタンク型のトゥルグトと,弓矢と小刀を武器にステルスに向いたメリエムというスキルの異なる3人のプレイヤーキャラクターがおり,アーリーアクセス版ではメリエムでプレイを開始する。
チャプターごとに半オープンワールドで描かれており,プレイヤーは近隣を探索したり,狩りや工芸品を作れたりと,できることの幅が広い。インタフェースとテキストが日本語化されているので,2026年に正式リリースするまで成長を見守っていたという人なら,今からプレイし始めるのも良いだろう。
 |
中世トルコを舞台にエルトゥールルの立身伝を描く。アクションADV「Ertugrul of Ulukayin」,6月12日にSteamで早期アクセス開始

Tekden Studioは,アクションADV「Ertugrul of Ulukayin」の最新トレイラーを公開し,2025年6月12日よりSteamで早期アクセス版を配信すると発表した。トルコの中世時代を舞台に,オスマン帝国の建国者であるオスマン一世の父,エルトゥールル・ガジの立身伝が描かれる。
インドネシアで語り継がれる“幽霊洞窟の盲人”
「The Blind Warrior」
インドネシアのRizero Studiosが開発中の「The Blind Warrior」は,オランダ植民地支配下にあった1860年代の西ジャワを舞台にしたゲームだ。もともと平和主義者だった主人公,バルダ・マンドラワタが,愛するものを悲劇的な事件で失ったことで復讐を誓っての孤独な戦いに身を投じていくというストーリーが描かれる。
洞窟で古代の精霊に訓練を受けたバルダは視力を失うものの,神秘的な技を習得し,残された感覚を強化し,反逆者や神秘主義者,虐げられた村人たちとの出会いを通し,森林の奥に潜む伝説と陰謀のつながりを暴いていくことになる。
バルダは実在の人物ではなく,1960年代に始まる「シ・ブタ・ダリ・グア・ハントゥ」(幽霊洞窟の盲人 / Si Buta dari Gua Hantu)という漫画本のキャラクターだが,長く植民地として苦渋を舐めてきたインドネシア人の魂でもあり,抵抗の象徴として絶大な人気を誇る。
ゲームプレイ面では,細かく分類するとインドネシアだけでも500の流派があるという武術の中から「プンチャック・シラット」が選ばれ,素手,剣,短槍など異なる戦法やミックスコンボ,ブロックやパリ―を含めたタイミングベースの多彩なアクションに加え,ステルスもフィーチャーされるという。現時点では発売日や日本語の対応などは未定だ。
 |
「The Blind Warrior」は,インドネシア生まれの“ツシマ”か“ウーコン”か? 現地のヒーロー“幽霊の洞窟の盲人”を描く[gamescom]
![「The Blind Warrior」は,インドネシア生まれの“ツシマ”か“ウーコン”か? 現地のヒーロー“幽霊の洞窟の盲人”を描く[gamescom]](/games/939/G093955/20250824006/TN/008.jpg)
gamescom 2025で,インドネシアのパビリオンに展示されていた,PC向けアクションアドベンチャー「The Blind Warrior」のデモに触れつつ,開発のRizero Studiosに話を聞いた。1960年から続く現地の人気コミック「幽霊の洞窟の盲人」をテーマに,盲目の戦士が宗主国オランダに反旗を翻す。
マサイ族の戦士”となってサバンナを駆け抜けろ
「HIRU: Mansa Assegai」
ステルス系アクションアドベンチャーは,ケニアでも開発されている。首都ナイロビを拠点にするKunta Contentによる「HIRU: Mansa Assegai」は,“砂漠のバイキング”という異名も持ったマサイ族の若き青年を主人公にし,妹を誘拐した密猟集団や民兵を追って,サバンナからジャングルや砂漠へと旅を続けていくという,比較的現代のケニアを描いた作品だ。
主人公は,サイスピアー(オル・アラム)と呼ばれる槍を手に戦い,背後から相手に忍び寄ったり,相手の銃器による攻撃を素早い槍の動きで弾き返したりという超人的な能力も開花させていく。
そんな「HIRU: Mansa Assegai」は,Africa Game Dev Programという地域の若い開発者を発掘するイベントが行われた2020年を機にプロジェクトがスタート。まだ情報は少ないものの,2026年11月への発売延期が決まった「グランド・セフト・オートVI」に関連して,「その前に発売できるよう懸命に開発中です」と言うコメントを公式Xで発表するなどしており,順調に開発は進められている様子だ。
2026年からは本格的なマーケティングも始まると思われる。まだSteamストアページはないが,イベントのスポンサーだったXbox向けにはストアページが存在する。
 |
ケニア産アクションADV「HIRU: Mansa Assegai」,開発を正式にアナウンスする映像を公開。誘拐された妹の軌跡を追うマサイ族戦士の物語

Kunta Contentは,アクションADV「HIRU: Mansa Assegai」の開発を正式にアナウンスするトレイラーを公開した。本作の詳細は明らかにされていないものの,1980年代のアフリカで密漁者に部族を襲撃され,妹を誘拐されたマサイ族の若者が,妹の消息と復讐のために戦う姿が描かれる。
著者紹介:奥谷海人
4Gamer海外特派員。サンフランシスコ在住のゲームジャーナリストで,本連載「奥谷海人のAccess Accepted」は,2004年の開始以来,4Gamerで最も長く続く連載記事。欧米ゲーム業界に知り合いも多く,またゲームイベントの取材などを通じて,欧米ゲーム業界の“今”をウォッチし続けている。
- この記事のURL:




















