イベント
そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]
面白いゲームを開発する手法の前にある,「考える力」の使い方が紹介されたセッションの模様をレポートしよう。
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/001.jpg) |
だらねこ氏は,現在アーリーアクセス版がSteamで「非常に好評」の評価を得ているRPG「いのちのつかいかた」を個人で開発しているほか,フリーのゲームデザイナーとして,主にコンシューマやスマホ向けのゲームの開発にも参加している。その場合,主にメインのゲームデザイナーを務め,若手の育成も行うことが多いそうだ。
そんなだらねこ氏が,「ジャンルを問わず,どんなゲームを作るときにも使える」ものとしてセッションの題材に選んだのは,「クリティカル・シンキング」だ。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/002.jpg) |
ゲーム開発では,「これは面白くなるぞ!」と思って企画したものが,いざ作ってみるとあまり面白くなく,作り直してもやっぱり面白くないので,また作り直し……とやっているうちに時間とお金が溶けてプロジェクト終了という,“恐怖のあるある”が起こりうる。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/003.jpg) |
だらねこ氏はその原因を「現実が見えていない」からだと話した。より具体的に言えば,仕様(原因)と,感想(結果)の間で,ゲームに何が起き,プレイヤーにどんな影響を与えているのかが見えていないのだという。そこを見ずに「こうなってほしい」「なってくれるはず」という希望的観測で作っても,狙ったものになる可能性は低い。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/004.jpg) |
また,仕様と感想のいいつながりが見えていても,それとは別に悪い結果へのつながりがあることに気づけないと,やはり失敗しやすくなる。
そういった見逃しを防ぎ,狙った面白さが実現できるようにするためのものがクリティカル・シンキング。日本語にすると「批判的思考法」だが,粗探しをするためのものではなく,情報を鵜呑みにしないで「疑問を持つ」ことを大事にしている思考法だ。分かりやすいところでは,「そんな装備で大丈夫か?」という「エルシャダイ」の有名なセリフもクリティカル・シンキングと言える。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/005.jpg) |
では疑問を持って何になるのか。「そんな装備で大丈夫か?」と聞かれたら,普通は「大丈夫かな?」と自分の装備を見直したくなるように,「考えるきっかけ」になる。
だらねこ氏は「考えが曖昧で甘い部分は,本人が気づいていない」と話し,疑問を持つことで考える対象になり,やがては問題の発見につながるとした。
人間の思考というものはバイアスがかかりやすく,自分の意見を肯定する情報を集めがちな一方で,自分の意見を否定する情報を無視する傾向がある。
これがゲーム開発であれば,最初に思いついたアイデアに固執して抜け出せなくなったり,そのアイデアのデメリットから目をそらしたり……といったことになってしまうのだ。
クリティカル・シンキングを使ううえでは,「人類は愚か」を基本スタンスにするといいという。「優秀な人であっても愚かである」という前提を置くことで,「今よりもっといい方法があるかもしれない」「何か見落としていることがあるかもしれない」という疑問を持ちやすくなる。
だらねこ氏は「自分を信じない。他人も信じない。でも,アイデアがもっとよくなる可能性は信じましょう」と呼びかけた。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/006.jpg) |
もちろん,疑問を持てばいいわけではない。「そんな装備で大丈夫か?」と聞いても,聞かれた人が何も考えずに「大丈夫だ,問題ない」と答えた結果,どうなるかは多くの人が知っている。だらねこ氏は「結果に対して,具体的な流れをイメージできる根拠で答えることが重要」だとした。
「そんな装備で大丈夫か?」という疑問に対しては,「この装備の防御力は相手の攻撃力より高いので,ダメージを抑えられる。問題ない」といった,原因と結果のつながりをきちんと説明できる答えが望ましい。
ありがちなのが,原因と結果の「外側」の部分に依存した回答だ。「あのレジェンドクリエイターが言っているのだから正しい」「最近話題のゲームで採用されているシステムだから取り入れよう」といった根拠による回答は一見綺麗だが,実は中身がなく,現実が見えにくくなっている。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/008.jpg) |
だらねこ氏は,疑問を持たずに曖昧な根拠でゲーム開発を進めても,後の工程では役に立たず,未来にはつながらないと話す。
それがコマンド式RPGの開発を例に紹介された。戦闘時のコマンドに入っている「通常攻撃」に対して,「これ,本当に必要ですか?」という疑問が上がるも,それに対して「RPGには通常攻撃があるのが一般的だから」という根拠で開発を進めたとする。そうすると,例えば通常攻撃の威力をどうするか,という問題が出てきたときに,調整がしづらくなってしまう。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/009.jpg) |
だらねこ氏はこの例に情報を付け加える形で,明確な根拠によるゲーム開発を説明した。
「魔法学校が舞台となるコマンド式RPGの戦闘コマンドに『通常攻撃』は必要ですか?」という疑問が上がったとする。それに対して「魔法を強力な存在として見せたいので,その比較対象として弱い攻撃がほしい」という,根拠が明確な回答を示せれば,その時点で通常攻撃の役割やダメージ感もつかめる。
また,そこで「弱いだけの攻撃なんて誰が使うの?」という疑問が上がったら,「それなら通常攻撃を3回行うと魔法が撃てるようにしよう」などといったアイデアにもつながる。
このように,疑問を持ち,根拠を明確にすることは,ゲームの「面白くしやすさ」につながるのだ。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/010.jpg) |
ただ,クリティカル・シンキングのメリットが分かっても,実行できるかどうかは別問題だ。だらねこ氏も「ここでセッションを終えても,8割9割の人はできないのでは」と話し,「疑うポイント」の紹介を始めた。
そのポイントは,ざっくり分けると「前提への問い」「方法への問い」「結果への問い」の3つとなる。
基本的な流れとしては,まず仕様策定の判断材料を集めるために,曖昧なところを明確化していく。これは主に「前提への問い」だ。
判断材料が集まったところで,「方法への問い」「結果への問い」を投げながら,最善の仕様を探っていく。その途中で曖昧な部分が見つかったら,また明確化に戻る。
だらねこ氏は「ゲームデザインに正解はないが,その仕様にする必然性はある」と語り,疑問を繰り返してそれを探すことが重要だとした。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/011.jpg) |
大まかな流れが分かったところで,次は“実演”。あるゲームデザイナーの上司として部下とやりとりする,という設定で展開された。
まず部下から「今作っているゲームで,新キャラとして魔法使いを追加する予定です。でも試しに追加してみても,何かパッとしないんですよね。なので攻撃力を上げて対応しようかと思います」という連絡が届く。
ここでだらねこ氏が最初に投げる疑問は,「前提の問い」と「方法への問い」が混ざったような「これ,パッとしない原因はダメージなの?」。
攻撃力を上げるということは,それによって最終的なダメージを上げたいと取れるが,そもそもダメージを出すことでパッとさせたいキャラなのか? というわけだ。
攻撃系の魔法使いならそれでいいが,状態異常系なら,見直すべきところは別にある可能性が高い。この疑問では,前提になるコンセプトと,それに対してやろうとしていることを明確にしようとしている。
部下からは「アタッカーとして作っているんですけど,他キャラとそんなにダメージが変わらなくて……」という返答があっため,問題なしと判断した。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/012.jpg) |
次の疑問は「今出ているダメージって本当にパッとしてないの?」。「パッとしない」という感覚は曖昧で人それぞれなので,数字を確認するのが狙いだ。
部下からは「他キャラが50くらいで,このキャラは52です。敵を倒せる攻撃回数も変わりません」という返答があり,認識にズレがなさそうなことが分かった。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/013.jpg) |
続いては「どのくらいのダメージが出たらパッとするの?」。こちらも数字による明確化を狙ったものだ。
部下からは「最低でも1.5倍くらい出れば,少ない攻撃回数で倒せる」「でっかい数字で気持ちよくなってもらいたいので3倍くらい」といった返答が来た,ということに。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/014.jpg) |
ここまでの流れで行ったのは,前提の確認だ。得られた情報をまとめると,「アタッカーである魔法使いのダメージが他のキャラと変わらず,パッとしない。他より少ない攻撃回数で倒せるよう,1.5〜3倍のダメージが出るくらい攻撃力を上げたい」となる。最初よりもかなり明確化された印象だ。
これをもとに,「それやった時,他キャラの価値は保てる?」という疑問を投げる。これは「結果への問い」で,やりたいことによって何が起きるのかの検討が目的だ。
より具体的にするなら「3倍のダメージをぽんぽん出してたら,他キャラはいらなくならない?」「このキャラだけ良くて,他キャラの武器が手に入っても嬉しくないのでは?」といった感じになるだろう。
「何が起きるのか」の想像は難しいが,だらねこ氏は,「脳内プレイ」で検証していくと見つけやすいと話した。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/015.jpg) |
他キャラの価値が保てるか否かは,ゲームによって異なってくる。4人のパーティメンバーの役割分担が重要なゲームだったら,3倍ダメージでもいいかもしれないが,4人すべてを魔法使いにできるようだと,ゲームバランスも他キャラの価値も崩壊しそうだ。
ただ,ここでだらねこ氏は,問題があるから絶対にダメというわけではないと補足した。3倍ダメージはゲームバランスを崩壊させるかもしれないが,「でっかい数字で気持ちよくなってほしい」というコンセプトには合っている。
ならばバランスを壊さずにでっかい数字を見せればいいということで,1ターン目に溜め,2ターン目に3倍ダメージといったシステムを採用するといった解決法もあると説明。「尖った仕様ほど問題が出るが,そこであきらめたら個性的なものは作れない」と話した。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/016.jpg) |
話は戻って,次に投げる疑問は「それで,何でこれ攻撃力を上げたいの?」。言葉を変えると,「ほかにもダメージを上げる手段はあるのに,なぜ攻撃力なの?」となる。
だが,現時点の部下にはこの疑問に対する判断基準がなく,「とりあえずアタッカーであればいいけれど……そこから先をどうすればいいのか分からない」という返答になった。
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/017.jpg) |
そこで,判断基準をはっきりさせるため,「前提への問い」となる「どんな時にダメージを出したいキャラなの?」を聞いてみる。
思いつかなければ,これまでに出ている材料から逆算するのもあり。どんな状況でもダメージを出すなら「攻撃力」,MP消費の大きい魔法でダメージを出したいなら「魔法自体の威力」,弱点をつくなどの「特定条件下での威力」を上げることが考えられる。
こういった感じで疑問を投げかけ,「せっかく魔法でいろいろな属性が扱えるし,それを活かして弱点を突いたときに目立ってほしい。普段のダメージは足りているので弱点特攻のパッシブスキルを入れます」ぐらいの返答が来たら,だらねこ氏はGOサインを出すという。
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/018.jpg) |
説明されると「割と当たり前の結論」にも見えるのだが,実際その通りで,だらねこ氏はこれを「必然性のある状態」と呼んでいるという。だが,この状態に至ったのは,数多くあった曖昧な部分を潰して明確化したからこそで,そのためのクリティカル・シンキングということになる。
今回の実演は上司から部下へ疑問を投げる形だったが,だらねこ氏としては「ディレクターにこそ疑問をぶつけるべき」と考えているという。ディレクターを責めるのではなく,ディレクターの判断を助けるような形で疑問を投げられれば喜ばれやすいそうだ。
ここまでを読んで,クリティカル・シンキングを身に付けたいと思う人もいるだろうが,もちろん誰でもすぐできるといったものではない。だらねこ氏は,「身に付いたと胸を張って言えるのは,情報を扱うときに意識しないで自然とクリティカル・シンキングできたとき」だと語った。
それまでは意識して使い,それを思考のクセにしていくといいという。ただ,「やる機会」を頑張って作るよりは,普段の生活の中で「ついでにやる」くらいがちょうどいいようだ。
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/020.jpg) |
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/019.jpg) |
だらねこ氏は説明を終えたあと,現在別の職場にいるかつての部下から「最近,ぼくの中にだらねこさんがいるんですよね」「仕様を思いつくと,ぼくの中のだらねこさんがツッコミを入れてくる」と言われたというエピソードを披露した。
だらねこ氏は,そのように自分の視点ではなく,「厳しいあの人だったら何と言ってくるか?」という他人目線で考えるといいのではないか,と話してセッションをまとめた。
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/021.jpg) |
「CEDEC 2025」公式サイト
4Gamer「CEDEC 2025」関連記事一覧
- 関連タイトル:
 講演/シンポジウム
講演/シンポジウム - この記事のURL:


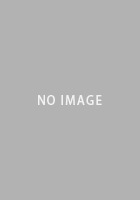








![そんな仕様で大丈夫か? 疑問によってゲーム開発をスムーズにする手法が紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250728053/TN/022.jpg)








