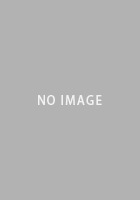イベント
メディアはインディーゲームのどこを見ている? 主要ゲームメディア6社がメディアへのアプローチ方法について真摯に答えたセッションをレポート
 |
その中でも代表的な手段がプレスリリースである。どうすればメディアに取り上げてもらえるのか――つまりメディアをハックできるかはインディーゲームコミュニティの中でもたびたび話題になり,ここ最近もSNSなどで白熱した意見交換が繰り返されている。
2025年11月15日に開催されたインディーゲーム開発者向けカンファレンス「Indie Developers Conference 2025」(IDC2025)で,「メディアが掲載したくなる,あなたのゲームの魅力を伸ばすには」と題した座談会が行われた。
同セッションには,企画趣旨に賛同した6つのゲームメディアから代表者が登壇。プレスリリースを受け取り,記事として発信する立場から,アプローチの仕方や情報の伝え方など,良いゲームを埋もれさせず届けるための実践的な視点が語られた。
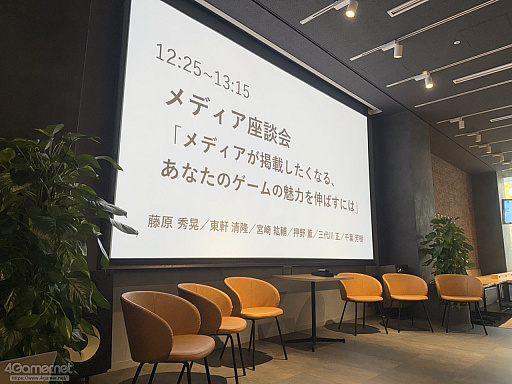 |
登壇者
イード ゲーム事業部 部長 宮崎紘輔氏(Game*Spark)
ファミ通.com 編集長 三代川正氏
電撃オンライン副編集長 押野 薫氏
IGN JAPAN 編集長 千葉芳樹氏
Gamer 編集長 東軒清隆氏
AUTOMATON 副編集長 藤原秀晃氏
本題に入る前に,セッション冒頭でファミ通.comの三代川氏が語った“登壇者のスタンス”を先に記しておきたい。
ゲームメディアは,ゲームを作る人たちがいてこそ成り立つ仕事であり,今回の座談会で語られた内容も,開発者に対して上から何かを指導したり,正解を示したりするためのものではけっしてない。あくまで情報を受け取る側として「こういう発信だとうれしい」「こう伝えてもらえると分かりやすい」と感じていることを共有し,少しでも参考になれば──という前提で話されている。
本稿は読みやすさのために内容を整理しているため,文字だけで見るとメディア側が断定しているように映る部分があるかもしれない。だが実際の会場では,登壇者たちは開発者に向けてまっすぐに,丁寧に語りかけるように問いに答えていた。この登壇者の姿勢は,読者にも誤解のないようここでひと言添えておきたい。
最初のテーマは「プレスリリースはどんな形だと読みやすいのか,書き方のコツは」というものだった。
 |
ファミ通.comの場合,1日あたりおよそ1000通のリリースメールが届くという。媒体で1日に掲載される記事は40〜50本ほどで,そのすべてがプレスリリース発ではない。SNSやDiscord,イベントでの発表を取り上げるものもあり,そもそも「目を通してもらえるか」の段階からすでに競争がある。
ファミ通.comのようにエンタメ総合を扱う媒体は各ジャンルからくるように,その日に届くプレスリリースの本数は媒体によって異なるが,どのメディアも数百通単位でリリースを受け取っている構造自体は変わらない。まずは“開封されるために何が必要か”という視点が語られた。
そこで重要になるのが,メールの件名にゲームのジャンルや特徴,発売日といった明確な情報を入れること。「掲載のご相談です」「リリースのご案内です」といった丁寧な文言自体はありがたい一方,それよりも内容が分かることのほうが圧倒的に重要だ。何よりもまず「そのメールを開く理由」が件名で示されているかどうかが入口になる。
また,「圧倒的好評」「ウィッシュリスト◯万人突破」といったアピールも価値はあるが,インディー界隈では見慣れた表現にもなりつつあるため,差別化にはつながりにくいという指摘もあった。
「このゲームは何が特徴か」が一瞬で伝わることのほうが重要で,“○○とローグライク要素を融合させた”といったように,既存タイトルやジャンルの“掛け合わせ”で説明できる作品ならそれが示されることでイメージしやすくなる。
もちろんこれは“リーチしやすさ”であって,記事化の際はそのままを書くのではなく,執筆担当者は作品のオリジナルの部分に真摯に向き合って自身の言葉でそれを紹介することを心掛けている……ということは伝えたい。
さらに実務的な話として,「本文にリンクを並べるより,PDFのリリースを添付してほしい」という意見も共有された。PDFならプレビューで一度に全体像が見えるため判断しやすい。逆に,素材がすべてzipにまとめられていると,解凍のひと手間がかかるぶん開封が後回しになりがちだ。
続いて話題に挙がったのは「プレスリリースはいつ送るべきか,何度送るのが適切か」。これについては,「開発側が出したいと思ったときが出しどき」というのが共通の前提として語られた。
“プレスリリースが読まれやすい時間帯や曜日”はメディアの体制によって違いがあるものの,たとえ深夜や休日に届いたメールでも興味を引かれる件名なら確認する。つまり冒頭の「件名と冒頭で埋もれないかどうか」がここでも重要となるわけだ。
回数についても,二通送られたからといって嫌がる編集者はいない(はず)。「発売予定を伝える一通」「発売しましたと知らせる一通」といった組み合わせも自然で,むしろ“見てほしい意志”が伝わるぶん目に留まりやすいという意見もあった。
一方で,“差分”があまりない情報を連続して送るのは避けたほうがいいという点も語られた。小さなアップデートごとに似た内容が繰り返されるより,Steamストアページ公開,体験版リリース,発売日告知といった節目に力を入れたほうがニュースとして成立しやすく,タイトルのアピールにもつながる。
また,一度取り上げられなかったからといって遠慮する必要はないという話も語られた。日々のプレスリリースの本数の関係もあって,メディアではどうしても日常的に見落としが発生する。だからこそ「念のためもう一度送る」は自然な行動であり,そこにネガティブな印象を持つ人はいない。
「ビルドやキーを送った場合,遊んでもらえるのか?」という問いにも触れられた。
これについては,どの媒体も「すべては難しい」と正直に語ったが,それでも“目に入る機会を増やす”という意味では大きな価値があると話す。たとえばレギュラー配信収録の前にちょうどネタを探しているタイミングで届いたキーなどは,その回で取り上げる候補に入ることがある。つまり「触れる理由」がある瞬間を生むための材料にはなる。
イベント取材についての質問ではさまざまな例が挙がり,媒体によってアプローチが大きく異なることが示された。たとえば「ある程度の候補は決めておくものの,最終的には現場で実際に触った担当者が強く推した作品が掲載候補に上がりやすい」という意見がある一方で,「出展タイトルの一覧が出た段階で扱う作品をしっかり決め,当日は全ブースを丁寧に見ていく」という運用も紹介された。
ただ,こうしたスタイルの違いがありながらも,事前情報の重要性や,現場で取材にあたるスタッフのインディーゲームへの探求心・熱量が決め手になるという点は共通している。「イベントで新ビルドを出す」「会場限定の要素がある」といった事前連絡は判断材料として非常にありがたく,また連絡手段については,媒体によってはメールよりSNSのDMやメンションのほうが早く気づきやすいという実務的な話も挙がっていた。
そして「案件(広告)はインディーでも打つべきか?」という質問が投げかけられた。返ってきたのは,「案件をいただけること自体はもちろんうれしい。しかし,初めての作品で無理をしてまで打つ必要はない」という率直な答えだった。
もちろん案件には案件なりの効果があり,それを否定する意図はない。ただ,開発者自身が数十万〜三桁万円といった広告費を捻出するのであれば,その予算は「まずゲームをきちんと仕上げること」や「次の作品の準備」に回したほうがいいと考えるのは,インディーゲームに向き合うメディア側としては自然な姿勢だ。
ゲームの情報を受け取り,その魅力を見つけて読者に届けることこそメディアの役割である。だからこそ案件については,「もしゲームがヒットし,次のステップへ進む段階で“ご縁”として相談をいただけたらうれしい」くらいのスタンスがこの場では共有されていた。
 |
いまは“対話”が重視される時代だ。特にインディーゲームは,それぞれが全く異なる環境や価値観のもとで制作される世界であり,著名なクリエイターやタイトルの成功体験に関わる話も大事だが,むしろそうではない一人ひとりの物語や試行錯誤の共有こそが重要になる。
自分に響く部分,自分では気づけなかった視点,足りなかった観点……そうした断片を拾い集め,正解・不正解というより“自分にとってどうか”を考えて消化していくことが大切だ。
その意味で,今回のようにメディアが自ら言葉を届け,自社のスタンスを開示する場が設けられたことにはとても大きな価値があると思う。ある種“手の内”を見せることでもあるが,それでも発信する意義があると判断して壇上に立った登壇者たちの姿勢にはリスペクトを感じる。
インディーゲームは本来,席を奪い合うものではなく,個々の感性や発想をどう形にし,それをどう届けるかという世界だ。それを追うメディアもまた同じように,インディーゲームという“場所”では情報を奪い合う競合ではなく,それぞれの得意分野や視点を示し,「自分の作品を理解して発信してくれそうだ」という信頼の選択肢として並ぶ存在であるべきだと思う。
会社としてみると競合でありライバルだが,インディーゲームを応援しサポートする立場としては同志とも言えるのだ。
同じメディア側の人間として大きくうなずけることが多く,自分自身のスタンスや考えを見つめ直すいい機会にもなった。この場で傍観者であったことに正直虚しさを覚えたが,それ以上に学ぶことが多く,このような話し合える場所がもっと必要だと感じられたも大きかった。
そしてこのセッションは,IDC実行委員会の一條貴彰氏がオープニングで語っていたことにも通じると思った。
IDCは,ヘッドハイ(デベロッパ),アクティブゲーミングメディア(パブリッシャ),産経デジタル(メディア)という異なる立場が集まり,インディー開発の現場を支える“三権”のような構造で運営されている。だからこそ,セッションには多様な立場・背景の人々が集まり,実感や悩みを共有できる空気がある。
今回のメディアセッションは,開発者へ向けた実践的なヒントであると同時に,インディーゲームを取り巻く関係者があらためて認識を共有する機会にもなったように思う。そしてそれは,インディーゲームに関わるメディアの一人としてとても有意義なものだと感じたのだ。
 |
- 関連タイトル:
 講演/シンポジウム
講演/シンポジウム - この記事のURL: