イベント
「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/002.jpg) |
登壇したのは,グラフィッカー/デザイナーのハフハフ・おでーん氏と,プログラマーのモチキン氏の2人。タイトルを見て「あれモチーフだよね?」とピンと来る人もいただろうが,内容として語られたのはSFネタではなく,2025年のインディーゲームシーンを語るうえで欠かせない1本となった「都市伝説解体センター」を「誰でもクリアできるゲーム」として成立させるための設計思想と,その結果として生まれたプレイヤーの反応について。
なぜ“脱落ゼロ”を目指したのか。どうやって最後まで遊び切れるゲームデザインを組み立てたのか。そしてその方針は,プレイヤーとコミュニティにどんな影響をもたらしたのか。墓場文庫の2人による“(セルフ)大喜利”という形でそれが語られた。その模様をレポートしよう。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/005.jpg) |
本題に入る前に2人は聴講者に「『都市伝説解体センター』を遊んだことがあるか」と挙手を求めた。かなりの数の手が挙がり,続く「では,ゲームクリアまでいった人は?」という問いで手を下げる人はいたものの,多くの人が引き続き挙手していた。
そののち投げかけられたのが次の問いだ。
「最近のインディーゲーム,クリアできたものいくつありますか?」
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/004.jpg) |
インディーゲームと一口に言っても,ゲームのボリュームやプレイ時間は作品によって大きく違う。
数時間で終わる短編もあれば,AAAタイトルに負けないボリュームとやり込み要素を持ち,数十時間〜それ以上を要求するタイトルもある。しかも毎日多くの作品がリリースされており,それにどう向き合うか,向き合えるかは(インディー/メジャー問わず)ゲーマーの“課題”だ。
おでーん氏も「年齢的にもしんどくなってきた」と率直に語っていたが,もちろんこれは年齢だけの話ではない。仕事や生活環境,ほかの娯楽との兼ね合いもあり,「遊びたい気持ちはあるけれど,エンディングまでたどり着けない」プレイヤーは決して少なくないだろう。
ゲームを最後まで遊び切る。それ自体がけっこうハードルの高い体験なのではないか。では,“クリアまで行けるゲーム”を意識して作ったらどうなるのか。
それを追求したのが「都市伝説解体センター」で,本セッションではその設計思想と結果を振り返るものであることが改めて示された。
話はまず2人がゲーム制作にチャレンジしたところから始まった。
遡ること8年前。当時2人は墓場文庫の前身となる制作ユニット「スカシウマラボ」として,マルチプレイ対応のハクスラ系RPG「サムライ地獄」というゲームを開発していた。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/006.jpg) |
勢い重視でゲーム開発にチャレンジしたが,それは見事に“エターナり”,まったくうんともすんとも動かない状態に。ゲーム作るの難しさを思い知らされ,サムライではなく開発者自らが地獄を見る状況となったという。
と,ここでひとつめの大喜利。お題は「サムライ地獄が頓挫した理由とは?」。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/007.jpg) |
![画像ギャラリー No.024のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/024.jpg) |
そのときの状況は,恋愛に目覚めたけどそもそも「どうやって付き合うの?」かが分からない,“恋に恋する”中学生のようなもの。ゲームを作ると思い立ったものの,「どうやって開発進めるの?」「どうやって終わらせればいいの?」というのをよく分からないままゲームを作っていた。
ゲームを作るという気持ちは走ったものの,これという目標もなく,何をゴールにすればいいのかも分かっていなかったのだという。
![画像ギャラリー No.025のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/025.jpg) |
世の中的には“根性と勢いでなんとかなる”みたいなところがあり,実際それでいけるときもある。しかしゲーム開発は全然ダメだと思い知らされたというモチキン氏。そもそものゲーム開発のきっかけが「BitSummitに出たい。そこでインディーゲーム開発者っぽい顔をしたかった」で,その“不純な動機”だけで作り始めて,ゲーム開発への考えが足りなかったと振り返る。
そうして大きくつまずいた2人は,「そろそろちゃんとやり直さないといけないよね」ということで,コロナ禍の2019年ごろ,“リハビリ”として新たなゲーム開発をスタートする。それが「和階堂真の事件簿」だ。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/008.jpg) |
ここで目標にしたのが,「自分たちの力量で絶対に完成できる規模感」「誰でもクリアできるボリューム感」のゲーム。1時間でクリアできる横スクロールのドット絵ミステリーアドベンチャーを“作り切る”ことを目指した。
「1か月で出す」と定めた締め切りは超えたものの,このタイミングから制作に加わったほかのメンバーの助けも得て,結果的には3か月で完成。2人にとって初めて作り切ったゲームであり,そして墓場文庫の名を広めるゲームとなった。
2人は同作を振り返り,開発コンセプトとして「リリースすること」「ちゃんと完成させること」を最初に置いたのが大きかったと話す。
“1か月間で何ができるか”を考えたとき,ミニマムなドット絵や,1画面横スクロールで人から話を聞くことで物語を進めるというシンプルな構造にすればコストもかからない。「こんな機能を入れたい」というアイデアも,“時間”という縛りのおかげで思い切って捨てられる。それなら一気通貫で作れるというモチベーションにつながった。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/009.jpg) |
ここで2つ目の大喜利。お題は「和階堂真の事件簿をリリースして,何に気づいた?」。
![画像ギャラリー No.026のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/026.jpg) |
「禅問答みたいになっちゃうんですけど」と前置きしつつ,リハビリだと気持ちを切り替えたつもりでも,「サムライ地獄」のときの“イキリ”が抜けておらず,開発している最中も「クリエイティブとは」「インディーゲームとしてのこだわりとは」といったことをつい考えてしまっていたと打ち明ける。
作り上げることをテーマにシンプルなゲームにしたものの,グラフィックスもあんまりよくない,ボリュームもそんなにない,ゲームシステムもシンプルすぎる……と「全然あかんよね」と思うところは多かった。
しかし,リリース後の反応を見て,実はそれが全部“いいところ”だったことを知る。
ゲーム開発をしていると「絶対この機能入れないとダメだよ」というアドバイスを受けることがよくあるが,実際にはそういった“足した機能”をプレイヤーがほとんど使わない,というケースも少なくない。
作り手が「こうありたい」「こういう作品を作りたい」と思っているイメージと,ゲームファンやプレイヤーが持っているイメージ。そのズレや対立している部分に,リリースしてみてやっと気づけた。つまり「リリースしないと分からなかった」ということだ。
![画像ギャラリー No.027のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/027.jpg) |
ミステリーにおける“どんでん”――どんでん返しは,一番最後の“オチ”としても機能する物語にとって非常に大きな要素だ。短い物語のため驚きの要素でいれたどんでんは,リリースしてみるとユーザーの反応は大きく,思ってた以上の20倍ぐらいの反応があったという。
ミステリー好きのモチキン氏は「和階堂真の事件簿」を通じて,ゲームでも,最後に“何かしらあること”をみんながけっこう期待していることを知れたのが大きかったと語った。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/010.jpg) |
こうして「和階堂真の事件簿」の開発とリリースで,3つの気づきが得られた。
まず1つ目は「タイパ・コスパを重視する層の存在」。冒頭でも伝えたとおり現代人は,すごく時間がない。2人は短いゲームへの好意的な反応をみて“時間に余裕がない人がけっこう多い”ということを,あらためて実感したという。
「和階堂真の事件簿」は作り切る,リリースするという目標もあってコンパクトなゲームになったが,結果としてユーザー側も“短い時間のプレイでフィードバックが返ってくる”ゲームを強く求めているのだと気づけた。
2つ目は「久しぶりにゲームを最後まで遊べたという実感」。「ゲームクリアできた」「ゲームクリアしたの何年ぶりだろう」という,“クリアできたこと”そのものへの声が多かった。
当時はスマートフォン向けのソーシャルゲームやオンラインのバトロワ系など,ストーリー的な終わりがない/見えないサービス型ゲームが主流で,“ゲームクリアをする”という体験自体がない人も多かった。そうした中で「エンディングまでたどり着いた」という達成感が,特別なものとして受け取られているのを感じたという。
3つ目は「自分でもできたという参加意識の高まり」。
これは主にクリアの達成感から生まれる,SNSなどでのバイラル効果の話だ。“クリアしたよ”とつぶやくこと自体が,人の輪の中に参加している気持ちや,承認欲求を満たす行為になっている。
ずっと遊べるゲームの「今日はここまで進んだよ」という報告と,“最後まで達成したよ”という報告では,やはり度合いも違ってくる。そういったコミュニケーションを楽しむ人がたくさん生まれたという意味でも,「こういうもの(作品)が世の中にあれば,結構喜んでくれる人がいるんだな」と感じられたという。
ここで得たものが,そのまま「都市伝説解体センター」につながっていく。
続く3つ目の大喜利のお題は「都市伝説解体センターの開発で活きた気づきとは?」。ここで2人がそれぞれ答えたのが「ゲームクリアの満足感を信じる」「ゲームが難しくてクリアをあきらめてた人,意外と多いのかも」だ。
![画像ギャラリー No.028のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/028.jpg) |
![画像ギャラリー No.029のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/029.jpg) |
冒頭の問いかけに戻るが,ゲームを遊びたい気持ちはあるのに,さまざまな要因で“遊びきれない”というのはよくある。難しすぎてすぐやめてしまう。覚えることが多すぎると,覚える前に諦めてしまう。昨今であれば,「ゲームで遊びたいけど苦手だから実況で見ている」という人も多いだろう。
「和階堂真の事件簿」の反応から2人が感じたのは,「ゲームで遊びたいけど“できない”という人が,想像以上に多いのではないか」ということだった。
その気づきをもとに,「都市伝説解体センター」開発を進めていくうえで3つのコンセプトを掲げたという。
1つ目は「最後までたどり着ける設計の徹底」。一番大きいのは,“ゲームオーバー”という概念をなくしたことだ。「ゲームなのにゲームオーバーないのか」と驚かれることも多かったが,それよりも「クリアしたときの満足感」を重視した。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/011.jpg) |
具体例として挙げられたのが,「詰まる箇所を極力なくすための施策」だ。
推理パートでは,選択肢で間違いが続くと誤答の選択肢は文字色のトーンが落ちる形で選択肢が絞られ,正解を導きやすくなる。会話パートでは,一度話した内容は下に送られ,新しいワードが上位に表示されて選びやすくなる。
誤答したときも,「間違いです」と強く指摘してペナルティを与えるのではなく,逆にキャラクター同士の面白いやり取りが発生する。「嫌な感じをさせない」「そこでテンションを落とさせない」ための工夫だ。
「ユーザーが迷わない」「辞めない」「諦めない」仕組み。2人はこれを「もういわば接待」と笑いながら,「なんとかなるはずだ」と前向きにゲームに取り組める設計を意識していたと語る。
実際の結果として,クリアしたあとのSNS投稿がかなり反響を呼び,クリア報告が過半数を占めたという。
2つ目が「途中離脱を防ぐ感情曲線」,3つ目が「1話=2時間を目安にしたタイパ設定」で,この2つは密接に関係しているため本稿では一緒に紹介していく。
「都市伝説解体センター」は全6話構成のアドベンチャーだが,章立てのゲームである以上,途中離脱はどうしても発生しやすくなる。
そこで1話を「短い話で分かりやすく,2時間ぐらいで遊び終われる」ようにしつつ,6話通しての“感情曲線”を先に作り,その上に物語を載せていったという。
新海 誠監督が自身の作品制作の資料で公開したことで知られる感情曲線は,作品を通して時間軸の中で「どこでどう感じてもらいたいか」という感情の流れをグラフ化したものだ。「都市伝説解体センター」ではそれを参考に,6話を通しての感情曲線を考えた。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/014.jpg) |
各章ごとの山場と,物語全体の引きとなるクリフハンガーを用意し,最後はきちんと感動までたどり着けるよう,その手前の中盤の盛り上げ方も意識して構成した。
当初は各章ごとに単体で順次販売する案もあり,「離脱されると売上につながらない」という事情も“できるだけ面白いシーンをうまいところに持っていこう”という考えにつながったとのこと。
特に大事にしたのが冒頭部分。一番最初の5〜10分を遊んで,「あ,面白くなさそうだからやめよう」となるケースは多い。そこで1話をまるまる遊んだときに,「この話ってどういう話なんだろう?」という“分からないところがいったん分かって”,そこで初めて“じゃあ続きやるかな”という関心が生まれるようなゲームにしたかったという。
そして「プレイヤーの生活に寄り添うゲーム体験の設計」。1話単体では連続ドラマのように1日1話を進めるイメージで構築。各話の中に見せ場を作りながら,次の話に進みたくなる引きを用意する。
また,“いつ終わるか分からない”のはプレイヤーにとってストレスや負担にもなる。全体では「6話で終わる」とあらかじめ見せつつ,各話の構成では「このターンが来たから,そろそろこの話も終盤だな」と分かるようなメリハリを付けた。
最初に物語全体の設計をして,あとから各話の細かい部分を埋めていくというやりかたも,「和階堂真の事件簿」から引き継いだものだ。
つかみにはもちろん“絵”も大事で,「和階堂真の事件簿」のときも,話が決まっていない段階でも「こういうシーンは先に作っちゃおう」と先に制作し,そこにシナリオを当てはめていったことがあったそうだ。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/015.jpg) |
こうして,続きに期待しながら「今日はここまで」と1日に少しずつ話を進められる仕組みを持ちつつ,「眠いけどもうちょっとやる」という一気読み的な遊び方もできるような構成とボリューム感の「都市伝説解体センター」は作られた。
その結果は実際どうだったか。それはSteamの実績のページに出ている数字としても表れている。
1話クリア実績の取得率は80%超え。全話クリアで見ると達成率54%と,かなり高いクリア率を記録している。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/016.jpg) |
さらに「面白かった」という人が「ほかの人にも遊んでほしい」と勧めるムーブも自然と生まれた。
これも「クリアしたからこそ」「短いゲームで操作も難しくないからこそ」の動きだろう。SNSなどで届くゲームの感想には「子どもと遊んでいる」というものから「70代の父に勧めた」まで,幅広い層が楽しんでいるという“報告”がSNSを中心に届けられた。
モチキン氏が「イケるやん」と手応えを得た“どんでん”も,SNS上のコミュニティ形成に大きな影響を与えた。
ネタバレになるため詳しくは語れないが,クリアした人の「たすけて」という反応がクリア済みの人たちの共感を呼び,プレイ中または興味を持った人の「どういうこと?」という関心を生む。
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/017.jpg) |
ネタバレはできないけど“この気持ちをちょっと知ってほしい。知ってもらいたい”――「たすけて」は,そういう思いから生まれたムーブメントでもある。
このコミュニティや現象は「怪異」と呼ばれ,現在進行形で“増殖”し続けているが,それは物語の力だけではなく「クリアできる」「最後まで遊べる」ゲーム設計があったからこそ,多くの人がエンディングまで到達し,強い感情を共有できた結果だと言えそうだ。
![画像ギャラリー No.032のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/032.jpg) |
なお,これは講演後の質疑応答で話題に出たことだが,この「怪異」については,今のところ日本独特の現象として“観測”しているそうだ。
このあたりはゲームコミュニティやSNS文化など,国や地域ごとのカルチャーの違いも出る部分ではある。例えば韓国ではローカライズのクオリティの高さに「自国のゲームかと思った」という反応もあったそうで,クリア後に話したくなるゲームだからこそ,国や地域といったコミュニティでの違いもまた興味深いものだ。
クリアしたからこそ話ができる。これはいろいろな部分でポジティブに働いたと,2人は感じている。
たとえばストアページのレビューは,「ちゃんとクリアしてからでないと書けないな」という気持ちが働く人は多いはずだ。つまりクリア率が高いと,「ちゃんとそこにエンディングまで到達したがゆえに発信される」レビューを書く人も多くなり,それは強い信頼性と発信力がある。
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/018.jpg) |
もちろんネガティブな意見もあるが,それは=マイナスではない。
レビューには「すごい面白い,やってみて」という絶賛があれば,「ちょっと自分には合わなかったな」という冷静な意見もある。どちらもクリアした人が自身の視点に立って語られるものであれば,その信頼性は高い。そしてそれは,「自分にはどっちだろう。やってみようか」という未プレイ者の興味につながる。
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/019.jpg) |
こちらも講演後の質疑応答の一つだが,コアゲーマー向けではなく「クリアできる」というコンセプトで作ったゲームではあるものの,「簡単すぎる」「これはゲームなのか?」という見られ方をすることもあったのではないか,またそれにどんな気持ちで構えていたのか,という質問があった(第三者的のようだが質問をしたのは筆者である)。
これに対して2人は,「全然自信はなかった」と正直に打ち明ける。今の形よりもっとシンプルだった段階では「ゲーム的な要素があったほうがいいのでは」と不安になったし,リリースを迎える段階でもそのような“構え”もなかったという。
発売後に「どこでこれがヒットすると思ったか」と聞かれることは多いが,当時はまったくヒットするとは考えておらず,「これ出したら怒られるんじゃないか」「ケチョンケチョンに言われるんじゃないか」と思っていたと振り返る。
発売後,このように高評価を受けた「都市伝説解体センター」だが,実際に「ゲーム性が弱い」というレビューもあるという。ただそこは,「エンディングを見させるためのゲーム体験」というテーマを掲げて作っていたからこそ,ある程度割り切って受け取れている部分だという。
それよりも,「和階堂真の事件簿」の発売後の反応でも形として出ていた「ゲームのエンディングまで行けば,ある程度満足してくれるプレイヤーは一定数必ずいる」ことを信じて作った結果が出ていることに注目しているそうだ。
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/021.jpg) |
「都市伝説解体センター」はパブリッシャである集英社ゲームズとも密に制作してきたタイトルだが,「ゲームクリアを最優先でいきましょう」という方針は共通認識だったという。
実際に開発中も,物足りなさではなく「シンプルすぎると離脱ポイントになるのでは」という部分での指摘や提案でサポートしてくれたという。
おでーん氏はクリアできるゲームを作ると“いいことあるかも”の例として,各ゲームアワードについて触れた。
「都市伝説解体センター」は,毎年東京ゲームショウ開催時期に実施される「日本ゲーム大賞」にて,2025年の年間作品部門・優秀賞を受賞した。それについて“クリアできるゲーム”だったことが大きな理由のひとつにあるのではないか……とその考えが語られた。
![画像ギャラリー No.033のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/033.jpg) |
「日本ゲーム大賞2025」受賞作まとめ。経済産業大臣賞はNintendo Switch 2が受賞。ゲームデザイナーズ大賞作品は桜井政博氏が直接プレゼン
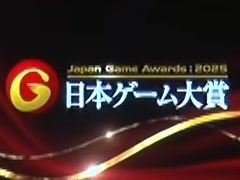
コンピュータエンターテインメント協会は本日(2025年9月23日),2024年度を代表するにふさわしいゲーム作品を表彰する「日本ゲーム大賞2025」の授賞式を実施し,各部門の受賞タイトルを発表した。
日本ゲーム大賞は,選考委員会の審議や複数の審査のほか一般投票の結果が影響する。
自身がプレイしたゲームを投票するとき,何を優先するかと考えると,やはり「クリアしたゲーム」である可能性が高い。好きなゲームが2つあってどちらかに投票するとしたら,最後まで遊んでの評価とラストまで見届けた体験の濃さは大きな指標になるだろう。
だからこそ「クリアできるゲーム」は票を入れてくれる人の幅が広がるというわけだ。
またメディアの投票企画などでも「記憶を消して遊びたいゲーム」として名前が挙がることが多いが,それもやはり“クリアしたからこそ”話題にしたくなるからだろうと語る。
そこから2人は“ゲームクリアできたという満足感”をユーザーに与えることの重要性をあらためて強調した。
“絶対にクリアしてもらう”というところに全振りして開発に挑んだ結果,短くても濃いゲーム体験を求めていた層に届き,そしてクリア体験を先にしたユーザーが共有し,拡散につながった。
タイパ・コスパを重視するユーザーが今はとても多い。その層をできるだけカバーしてあげられる作品を用意することは,インディーゲーム開発においてひとつの大きなポイントになり得るのだ。
最後にモチキン氏は,「(サムライ地獄のように)中途半端にゲームを作ってイベントとかに出すと,ずっとそれをイジられ続けます」と,「ちゃんと作り切ること」の重要性を話した。
「サムライ地獄」は,今でも「いつ発売ですか?」と擦られるという。「(まだ言う人は)全員ブロックしたろうか」と冗談めかしながら,中途半端な状態で表に出してしまったときの教訓としてそれを伝えた。
![画像ギャラリー No.022のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/022.jpg) |
衝動で走り出せてしまうこと。その衝動から生まれたものや伝わる“なにか”がインディーと呼ばれるモノの根源にあると思う。
“不純”と自らが語った「BitSummitに出たい」という動機も,インディーバンドやアーティストでいえば,「あのライブハウスに出たい」「あのフェスの舞台に立ちたい」と思う感覚に近いものを感じる(※という話を今年のBitSummit the 13thでしているので,ご興味がある方は[こちら]をどうぞ)。
[インタビュー]「都市伝説解体センター」ハーフアニバーサリー。墓場文庫×集英社ゲームズに聞いた,半年の歩みとインディー的カルチャーの話
![[インタビュー]「都市伝説解体センター」ハーフアニバーサリー。墓場文庫×集英社ゲームズに聞いた,半年の歩みとインディー的カルチャーの話](/games/649/G064901/20250818034/TN/016.jpg)
ゲーム開発チーム・墓場文庫が制作し,集英社ゲームズがパブリッシャを務める「都市伝説解体センター」がリリースから半年を迎えた。2025年の話題作となった本作のいまとこれから,そしてインディーのカルチャー“的”な話を,ハフハフ・おでーん氏と林 真理氏に聞いたインタビューをお届けしよう。
つまりこのセッションはその衝動を否定する話ではまったくなく,「走り出すきっかけはどんなに些細でもいいけれど,“最後まで作り切る”ことをちゃんとやろう」という,とても地に足のついた内容だと感じた。
ゲームに限らず,ものづくりや仕事には「こうしたい」「こうあるべきだ」という信念や言いたいことがつきまとう。でも,それを全部抱えたままでは前に進めないし,時には完成にたどり着けないこともある。
そのとき,そこで投げてしまうのか。それとも残したい核だけを残し,切るべきものを切り,どこかで折り合いをつけてでも“作り上げる”のか。
一度でも「作り切った」「最後まで届けられた」という経験は,状況や結果がどうであれ,“できた”という自己肯定感と,できなかった部分の「次はどううまくやるか」という前向きな視点につながっていく。
今回のセッションは「ゲームをクリアできる」設計だけでなく,広くモノづくりや仕事における「やり切ること」の大切さを実感させてくれる内容だった。それは聴講していたゲーム開発者だけでなく,“ものづくり”や日々の仕事に向き合う多くの人々に響くはずだ。
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / 「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/001.jpg) |
なお,4GamerではこれまでCEDEC 2025のセッションレポートやインタビュー,対談企画などで「都市伝説解体センター」制作の裏側や考えについて伝えている。
関連記事もチェックしてもらえると本稿の解像度もまたさらに上がるかと思うので,是非チェックしてほしい。
「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート詳報版。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]
![「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート詳報版。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250728038/TN/033.jpg)
3か月で30万本を売り上げたというインディーゲーム「都市伝説解体センター」。そんな本作を開発するにあたって,「3つの掟」を定めたという。スマッシュヒットとなった本作はどんな環境で生まれたのか,講演で語られた内容を紹介しよう。
[インタビュー]「都市伝説解体センター」ハーフアニバーサリー。墓場文庫×集英社ゲームズに聞いた,半年の歩みとインディー的カルチャーの話
![[インタビュー]「都市伝説解体センター」ハーフアニバーサリー。墓場文庫×集英社ゲームズに聞いた,半年の歩みとインディー的カルチャーの話](/games/649/G064901/20250818034/TN/016.jpg)
ゲーム開発チーム・墓場文庫が制作し,集英社ゲームズがパブリッシャを務める「都市伝説解体センター」がリリースから半年を迎えた。2025年の話題作となった本作のいまとこれから,そしてインディーのカルチャー“的”な話を,ハフハフ・おでーん氏と林 真理氏に聞いたインタビューをお届けしよう。
「違う冬のぼくら」×「都市伝説解体センター」クリエイター&パブリッシャ対談。個人開発とチーム開発,それを支える出版系パブリッシャの話

TGS 2025で講談社ゲームラボが配布した「ゲームラボマガジンVol.2」巻頭特集の“延長戦”。ところにょり氏とハフハフ・おでーん氏に加えてパブリッシャとして関わる片山裕貴氏と林 真理氏に参加してもらい,関西インディー,インディ―ゲームの個人&チーム開発の違い,パブリッシャの考えなどを話してもらった。
- キーワード:
- PC:違う冬のぼくら
- Nintendo Switch:違う冬のぼくら
- PS5:違う冬のぼくら
- :違う冬のぼくら
- /:違う冬のぼくら
- :違う冬のぼくら
- Nintendo Switch 2:違う星のぼくら
- Nintendo Switch 2
- アドベンチャー
- SF
- ところにょり
- パズル
- 協力プレイ
- 講談社
- 日本
- Nintendo Switch:違う星のぼくら
- PC:違う星のぼくら
- Nintendo Switch:都市伝説解体センター
- Nintendo Switch
- CERO B:12歳以上対象
- プレイ人数:1人
- ホラー/オカルト
- 集英社ゲームズ
- 墓場文庫
- PS5:都市伝説解体センター
- PS5
- PC:都市伝説解体センター
- PC
- 企画記事
- インタビュー
- 編集部:Junpoco
- 編集部:だび
- TGS 2025
- 東京ゲームショウ
- 関連タイトル:
 都市伝説解体センター
都市伝説解体センター
- 関連タイトル:
 都市伝説解体センター
都市伝説解体センター
- 関連タイトル:
 都市伝説解体センター
都市伝説解体センター
- この記事のURL:
キーワード
- PC:都市伝説解体センター
- PC
- アドベンチャー
- CERO B:12歳以上対象
- プレイ人数:1人
- ホラー/オカルト
- 集英社ゲームズ
- 墓場文庫
- PS5:都市伝説解体センター
- PS5
- Nintendo Switch:都市伝説解体センター
- Nintendo Switch
- イベント
- 編集部:Junpoco
- IDC2025
(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES
(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES
(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES









![「都市伝説解体センター」が挑んだ“優しいゲーム設計”とは――プレイヤー全員をクリアまで導く仕組みと,作り切ることの力[IDC2025]](/games/649/G064901/20251121032/TN/038.jpg)











