イベント
琵琶を壊して録音,木材で建築を検証――開発陣のこだわりが生んだ武侠オープンワールド「風燕伝:Where Winds Meet」が描く五代十国時代の乱世
 |
風燕伝は,中国史上最大の動乱期といわれる五代十国時代を舞台に,武侠の精神とオープンワールドの自由度を融合させた意欲作だ。開発を手掛けるEverstone Studioが目指すのは,東洋の美学と哲学を世界に発信する,かつてないスケールのアクションアドベンチャーRPGだという。
本作は基本プレイ無料のタイトルとして,PlayStation 5,PCでの展開が予定されている。中国ではすでにリリースされており,半年間で3000万ダウンロードを記録。その成功を引っ提げて,世界市場への挑戦が始まろうとしている。
 |
 |
Everstone Studioは,高品質なオープンワールドゲームの制作に特化した新興の開発スタジオだ。メンバーは戦闘演出,レベルデザインなど各分野のエキスパートで構成され,全員が深いゲーム愛とプレイヤー視点を共有している。彼らが掲げる理念は明確で国際的なゲーム制作手法を導入しながら,東洋芸術が持つ独特な美学と哲学を全世界に発信することだという。
そんな開発陣が手がける本作では,史実と幻想が融合した没入感のある世界観を,最先端技術を駆使して表現。広大な世界における自由度と柔軟な探索体験の実現を目指している。
 |
風燕伝の舞台となる五代十国時代は,唐朝の崩壊から宋朝(北宋)の成立までの約70年間,中国が分裂と統一を繰り返した激動期だ。開発チームがこの時代を選んだ理由について,Narrative DesignerのAvery Wang氏は「映画やドラマでもあまり描かれてこなかった新鮮さがプレイヤーの好奇心を刺激すると考えた」と語る。さらに,「唐と宋という2つの大王朝に挟まれた動乱の時代だからこそ,ドラマティックな表現が可能になる」とも語っていた。
物語は,主人公が「江湖」と呼ばれる武侠の世界に足を踏み入れ,自らの出生の謎を解き明かしながら,裏切りと秘密に満ちた世界を旅する内容となっている。メインストーリーは「光」と「影」の2つの側面から構成され,「影」の部分では歴史上の人物や事件が断片的に描かれるという。
 |
興味深いのは,歴史的事実をゲーム体験に昇華させる手法だ。例えば,宋朝が唐の貨幣使用を禁止した「宋初収唐銭」という政策や,歴史上の人物「銀(イン)」にまつわる物語などが,シナリオの核として組み込まれている。この史実とフィクションを巧みに融合させるストーリーテリングは,まさに金庸※作品を彷彿とさせる。「射鵰英雄伝」や「天龍八部」でも実在の歴史事件に架空の人物を絡ませる手法が使われているが,本作もその伝統を見事に継承していそうだ。そして歴史部分は専門家による監修のもと,博物館や文化局とも連携し,史実に忠実な表現を心がけているそうだ。
※金庸:中国武侠小説の巨匠。代表作は「射鵰英雄伝」「神鵰侠侶」「天龍八部」「笑傲江湖」「鹿鼎記」など。史実と虚構を巧みに織り交ぜた壮大な物語と魅力的なキャラクターで,その作品はアジア全域で愛されている
もちろん,歴史知識がなくても楽しめるよう配慮されており,開発チームは「歴史上の人物や物語の中から最もドラマティックな部分を選んでゲーム内で再現している」と説明していた。例えば,開封で出会う「太ったおじさん」は,歴史に詳しいプレイヤーなら「もしかしてあの人物では?」と推測できるヒントが隠されているが,知らなくても愛らしいキャラクターとして楽しめるという二重構造になっている。
 |
本作の世界は,神秘的な洞窟から雄大な草原,穏やかな田園から活気溢れる都市まで,12以上の地域と20以上のダンジョンで構成される。中国語版では「開封」や砂漠地帯である「河西」など,異なる地域のマップも追加されており,約1.5〜2か月ごとに新たな地域が実装されているという。
特筆すべきは,世界に息づくNPCたちの存在感だ。単なる背景オブジェクトではなく,生きた個体として振る舞う彼らは,プレイヤーの行動に対して多様な反応を示す。喧嘩を仕掛ければ反撃してきたり,逃げ出したりするし,時には役人に通報することもある。開封市だけでも,行動様式,衣装,名前,嗜好がそれぞれ異なる1万人以上のNPCが登場するという。
街には得体の知れない商品を扱う行商や腕試しを挑む武芸者もおり,武侠世界が立体的に描かれている。武侠小説などを読んだ経験がある人がプレイすれば,そうそうこんな感じと思うはずだ。
筆者は武侠小説(主に金庸作品)のファンだが,街中で「おい俺様の前を素通りとはいい度胸だな」と声をかけられたときは,「おお,これぞ江湖だ」と興奮した。
 |
酒場で出会った老人が実は隠れた達人だったり,路地裏で怪しげな秘伝書を売る商人がいたりと,武侠作品ではお馴染みの展開も多そうで,それだけでワクワクしてくる。「最近,西の山に奇妙な武芸者が現れたらしい」といった何気ない会話から新たな冒険が始まる予感は,「笑傲江湖」の令 狐冲が各地を放浪しながら出会う偶然の連続を彷彿とさせる。本作をプレイしていると,自分も金庸作品の主人公になったような没入感が得られるのだ。
ちなみに,中国で制作される武侠を題材にしたゲームは,武侠の予備知識を持っていることが前提に作られていることが多く,本作をプレイしていても細かい説明もなく武侠用語が出てくる場面はある。ゲームの機能としての説明は都度入るとはいえ,世界観をより深く理解したい場合などは以前掲載した記事を参照してほしい。
連休にアジアンエンターテイメントに触れよう! 武侠ゲームを遊ぶ前に知っておきたい10のコト
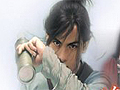
4Gamerでも見かけることが多くなった「武侠」という言葉をご存じだろうか。武侠とは,中国武術などが出てくる娯楽文芸ジャンルの一つで,中国や韓国などでは大衆文化として根付いている。だが,日本での認知度はそれほど高くない。ここ数年で武侠ゲームが増えてきたので,それらを楽しむうえで押さえておきたい用語/設定を紹介する。いつもより長めの休みを使って,武侠の知識を深めよう。
また,世界の表現において,リアルタイムで変化する昼夜や天候システムも重要な役割を果たしている。時間ごとの光の表現や天候の変化が動的に反映され,プレイヤーの没入感を高める。
コンセプトアーティストのZHONG Zhou氏は「200TB以上の写真素材を集めて,細部まで歴史的・現実的な再現性を高めることに注力した」と語る。特に推奨する場所として挙げられた「燓楼(パンロー)」は,当時の娯楽の中心地として複雑な構造と美しい外観を持つ建築物で,その再現には相当な苦労があったという。
さらに,開発チームのこだわりは,デジタルでの制作だけに留まらない。建築物をゲームに実装する前に,実際に木材で物理的な小型モデルを作成し,その構造が建築として成立するかを検証しているのだ。美しい外観を保ちながらも,柱や梁の配置が不自然でないか,建物として合理的な構造になっているかを手作業で確認。この地道な作業により,ゲーム内の建築物もリアリティのある,説得力を持った存在となっている。なお,一度作った屋根などのパーツはほかの建物にも応用できるため,開発効率の向上にも寄与しているという。
 |
 |
 |
 |
7種の武器と40種の武術が生む無限の戦闘スタイル
武侠といえば,なんだかんだいっても戦いが華であり,本作でも戦闘システムが大きな魅力の一つになっている。剣,槍,斬馬刀,双剣,縄鑣,扇,傘という7種類の武器系統が用意され,各武器には1〜3種類の対応する武術を組み合わせられる。中国語版では10種類以上の武術が実装されており,今後も拡充予定だ。これにより,プレイヤーは自分だけの戦闘スタイルを自由に創造できる。
また武術とは別に「奇術」と呼ばれるスキルシステムも充実している。獅子咆哮,蝦蟇功,太極拳,点穴など,40種類以上の武侠に由来する奇術を習得可能だ。これらは武器に依存しない特殊能力として,戦闘の可能性を大きく広げる。ちなみに,試遊では熊の動きをみて太極拳の基礎を学ぶという展開があった。また,筆者は今回試せなかったが,「軽功」を使えば広大な世界を素早く駆け巡れる。
 |
PC版の操作体系はコントローラ,キーボード&マウスの両方に対応している。基本的な移動や攻撃は一般的なアクションゲームと同様だが,武侠らしい独特な要素も多い。特に移動面では,×ボタンの跳躍(ジャンプ)を長押しすることで「軽身功」が発動し,空中滞在時間が大幅に延長される。さらに跳躍中に○ボタンを押すと空中ダッシュも可能で,宙を舞いながら移動できるのだ。
※今回の試遊は,PCにPlayStation用のコントローラを接続して体験した
戦闘では□ボタンで軽攻撃,△ボタンで重攻撃を繰り出し,L1で防御,R1で受け流しを行う。方向キーで武術や奇術を切り替えられるなど,多彩な技を瞬時に繰り出せる設計になっている。これらの操作を組み合わせることで,地上戦から空中戦まで,まさに武侠の達人のような立体的な戦闘が楽しめる。
流派システムも独特だ。11の流派がそれぞれ独自の武術と規定を持ち,プレイヤーは自由に所属を選べる。どの流派に属さなくてもすべての武術や奇術を習得可能で,他流派の技を盗み習うことも可能だ。
そうなると,どの流派にも所属しなくてもよさそうにも思えるが,所属する流派のルールに従うことで奨励ポイントが得られ,特別なアイテムと交換できるというメリットがある。なお,ルールを破るとポイントが減るペナルティがあり,天泉という流派では,ルールに従わないと毎日のログイン時にランニングをさせられるといったユニークな設定もあるそうだ。
 |
戦闘モーションの制作には,香港電影金像奨および台湾金馬奨「最優秀アクション設計賞」受賞者のトン・ワイ氏を武術指導として招聘。さらに北京舞蹈学院副教授で2022年冬季五輪開会式分会場副監督のティエン・ティエン氏がダンスアクションを監修し,モーションキャプチャ技術を駆使して武侠アクションの真髄と優美な動きを再現している。
本作の大きな特徴の一つが,基本プレイ無料というビジネスモデルの採用だろう。開発チームは「より多くのプレイヤーにゲームを遊んでほしい」という思いから,価格設定によるハードルを設けないことを選択した。
重要なのは,ゲーム内の数値に影響する課金要素が一切ないという点だ。課金対象は外観アイテム,スキルの視覚効果,乗り物など,プレイヤーが「喜びを感じる」要素に限定されている。これにより,1万円の課金者と10万円の課金者でゲーム体験が変わることはなく,すべてのプレイヤーが公平な体験を持てる設計となっている。
 |
実際にプレイしてみるとクエストもかなり多そうで,外見にこだわらないのであれば無料でたっぷりと遊べるように感じた。そして中国での運営実績がこのモデルの成功を証明している。半年間で3000万ダウンロードを達成し,課金要素が数値に影響しないことでプレイヤーとの信頼関係が築かれ,一時的に離れても新しいコンテンツが追加されると多くのプレイヤーが戻ってくるという好循環が生まれているそうだ。
本作にはシングルプレイとマルチプレイの2つのモードが用意されている。シングルプレイは150時間以上の完全なソロ体験が可能で,どっぷりと武侠世界に浸れる。強制的なソーシャル要素もないため,自分のペースで物語を楽しめるのが魅力だ。
一方,マルチプレイでは最大4人のフレンドを自分の世界に招待して共に探索できるほか,協力競技や団体戦,最大30対30の大規模PvP,共同建築なども楽しめるという。仲間と共に武術を練習したり,五禽戯(ごきんぎ)を踊ったり,投壺(的当てゲーム),釣り,中国蹴鞠(しゅうきく)といったミニゲームで交流することも可能だ。
 |
建築システムも充実しており,1000種類以上の建築パーツを使って自分だけの建物を構築できる。ゲームに設定されているマップを直接利用することも,まったく新しい理想の楽園をゼロから創造することも可能という自由度の高さが魅力だ。
グラフィックス面は,最大画質設定で4K60fpsの滑らかな動作に対応している。しかし,本作の真価は映像美だけではない。サウンドデザインにも並々ならぬこだわりが込められている。
オーディオデザイナーのYida氏によると,屋外探索時には中国の楽師がプレイヤーの傍らで演奏しているかのようなランダムな音楽が流れ,それが鳥の鳴き声や水の音など,環境音と融合する。中国のあらゆる楽器や民謡,各地方の戯曲などが取り入れられ,ボス戦では緊張感のある音楽に切り替わるなど,状況に応じた変化も用意されている。
音響効果制作への思いは強く,本物の野菜を叩いたり潰したりして効果音を制作したという。キャベツやセロリで打撃音や骨折音を、トマトを潰して血しぶきの音を再現するなど、リアリティ追求への執念は尋常ではない。さらに,ゲーム内のカットシーンで琵琶が壊れる音を表現するために,実際に数本の琵琶を購入して破壊して録音したというエピソードもある。洞窟の音響では,古琴をクレジットカードで擦るという独創的な方法で,奇妙でありながらも自然な音を作り出したという。
 |
 |
開発チームが考える武侠の魅力は「個人の努力で一つのゴールを達成する」という,努力が報われるロマンスにあるそうだ。そのほかにも「人と人の関係性」にもあり,多くの武侠作品では,戦闘だけでなく,人々との恩義,憎しみ,愛情といった複雑な人間関係が描かれる。「風燕伝:Where Winds Meet」というタイトルにもその意味は込められており,「風/Winds」はいわゆる縁を表しているそうだ。
 |
武侠という文化的要素を海外に伝えるうえでの最大の苦労はローカライズだという。中国独自のシンボルや文化的な要素を,元の文化的な要素を残しつつ,いかに理解してもらえるように翻訳するかが非常に大変だったと開発陣は語る。しかし,「武侠の本質である『個人の努力で世界を変える』という精神は,世界共通の認識」であり,この普遍的なメッセージに焦点を当てることで,文化的な障壁を越えてプレイヤーに共感してもらいたいと考えているそうだ。
 |
また,中国での半年間の運営では,議論が活発に交わされているという。特に印象的なのは,ストーリーに対する「考察」を行うプレイヤーが多いことで,開発者自身も驚くような解釈が生まれている。メインキャラクターだけでなく,村人(NPC)の物語を題材にした二次創作も盛んに行われており,プレイヤーの熱意が開発チームの「栄養」になっているという。
五代十国時代は動乱に満ちた悲劇的な時代だが,プレイヤーに重い負担を感じさせたくないという考えから,歴史の事実に関係しない部分でコミカルな要素を追加し,バランスが取れるように設計されている。香港映画「カンフーハッスル」のように,悲しいストーリーの中に笑える要素を取り入れることで,プレイヤーが遊びやすいように工夫されているのだ。
 |
グローバル版は年に4回程度の大型アップデートを想定しており,中国版のコンテンツに徐々に追いついていく設計となっている。ローンチバージョンではチャプター1と2が完結した状態で提供され,現在開発中のバージョンでは複数のエンディングの可能性も増やしているという。
武侠と聞くと構える人もいるかもしれないが,日本のプレイヤーにとって親しみやすい要素もあるそうだ。「ゼルダの伝説」シリーズのようなオープンワールドの遊び方や,フロム・ソフトウェアのゲームで見られるような断片的なストーリーテリングの手法など,日本のプレイヤーが慣れ親しんだ要素が多く含まれているため,文化的な背景を気にせず楽しめるはずだと,開発陣は自信を見せる。
短い試遊時間ではあったが,本作からは開発チームの「武侠愛」がひしひしと伝わってきた。とくに印象的だったのは,派手なアクションだけでなく,静と動のメリハリが絶妙なことだ。激しい戦闘の後に茶館で一息つき,店主と世間話をしていると,ふと「江湖の掟」について語り始める。こうした何気ない会話の端々に,義理と人情,恩讐と因縁といった武侠の世界観が息づいている。
 |
グラフィックスの美しさも特筆すべき点だ。夕暮れ時の街並みは息を呑むほど美しく,瓦屋根に反射する夕日や,路地から立ち上る炊事の煙まで丁寧に描かれている。そこを駆け抜ける爽快感は,まさに武侠映画の主人公になったかのようだ。戦闘も単なるボタン連打ではなく,相手の動きを見極めて受け流し,隙を突いて反撃するという駆け引きが楽しい。とくに奇術を絡めた戦いは見た目も華やかで,決まったときの達成感は格別だった。
基本無料でここまでの品質を実現している点も驚きだ。課金要素が外見変更のみという潔さも好感が持てる。中国での成功も納得の完成度で,2025年内のグローバルリリースが今から待ち遠しい。願わくば,日本語音声も実装されることを期待したい。
「風燕伝:Where Winds Meet」は,武侠とオープンワールドという2つの要素を高いレベルで融合させた意欲作として,2025年のグローバルリリースに向けて着実に準備が進められている。東洋の美学と哲学を世界に発信するという壮大な目標を掲げる本作が,どのような形で世界のプレイヤーに受け入れられるのか。その答えが出る日は,そう遠くない。
「風燕伝:Where Winds Meet」公式サイト
- 関連タイトル:
 風燕伝:Where Winds Meet
風燕伝:Where Winds Meet
- 関連タイトル:
 風燕伝:Where Winds Meet
風燕伝:Where Winds Meet
- この記事のURL:




















